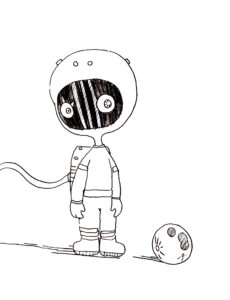「髪型を変えたの」
隣を歩くリスは、そう言って前髪を少し触った。私は、それほど彼女の変化に気がつかなかった。むしろ、彼女がひたすらにつま先を見つめていることが気になっていた。
「へえ、いいね」
私は言った。口の中に団栗のカスが詰まっている。もぞもぞ舌を動かす。
「あなたは、髪型を変えないの?」リスは言った。「もう五年も同じ髪型じゃない。ショートにしてみたら?」
彼女は、じっと私の髪を見つめた。
「切るの、お金がかかるじゃない」と私。あんまり綺麗な毛じゃないから見ないでほしい。首筋に生えた長い毛を、ちょいちょい触る。
「ええ、わかる」リスは言った。「もともと、その髪型、あなたにあっているもの」
二人は、木の館にやってきた。この森の中で、一番大きな館だ。およそ百年前から建っているわけだけど、ここのご主人は、最近になって、カフェを開くことにした。なぜなら、唯一の息子が、館を継がずにとなりの森へ出てしまい、管理に困った主人は、館をカフェに変えたがっていたフクロウのおやじと相談し、管理をフクロウのおやじに任せることにしたからだ。今では、館の管理は、主人とフクロウのおやじがやっている。
私は、その辺の事情は、足元をあるく蟻ほどにしか気にかけなかった。蟻たちは、よく見えない目の代わりに、触覚を動かして、必死に食べ物のありかを探している。リスである私たちなら、「すぐ先に軽食を出すカフェがありますよ」と言うこともできるけど、なにせ、私たちは自分たちのことで忙しかったし、アリもアリで、カフェのメニュー表が読めないので、行ったところでなんの得にもならなかった。
私は、静かに木漏れ日の中を歩いた。
「今は、なんの仕事をしてるの?」私は、隣のリスに訊ねた。
「キツネのところで、株の勉強よ」早口でリスは答えた。「彼、頭がいいの」
カフェの中に入り、二匹は、胡桃のケーキを注文した。
待っている間、二匹は、窓の外から、キノコたちの演奏を聞いた。キノコたちは、頭上から落ちてくる朝露を受け、ぼん、ぼぼん、ぼん、と分厚いかさを鳴らしている。朝露を落としているのは、これまた、自分たちと同じリスだった。綺麗にととのった毛並み。藍色に染めた、お洒落なしっぽ。彼は、それを振りながら、葉にくっついた朝露を落としていく。観客のウサギが、心地よさそうに耳を振った。相方のウサギも、嬉しそうに鼻をひくつかせる。
「あなたは? 木の実磨きの仕事を続けているの?」
胡桃ケーキを待ちながら、リスが訊ねた。
「半分半分」
「その半分って?」とリス。
「たまに、演奏するの」
リスは、目を丸くし、小さな前歯を出して笑った。
「そうなの? 懐かしいわね。どこで?」
「紅葉のレストラン。小さいところだよ。不定期だけど、なくちゃならないものなの」
「私も、時折思い出して、ピアノを弾くわ」リスは、鼻を引くつかせた。「昔は、偉大な演奏家になるって意気込んでたけど。いまは、弾いているだけで充分」
胡桃のケーキは、まだ来なかった。だから、私は、紙ナプキンで折り紙を始めた。外では、キノコの演奏家が、流行りのビートを利かせている。彼は、興奮の波に乗って、枝の上を走り抜ける。
「もう、演奏家になる気はないの?」と私。
「なれたら、すごくいいわ。でも、私には向いていないとわかったの。そういうのって、努力とかの問題じゃないのよ」探すように、リスは手で宙をかき混ぜた。「素質、運。いいえ、多分、鍵だわ」
「鍵?」
「そう。自分の中にある、ドアの鍵よ。鍵は、さまざまな要因が重なって、作りあげられていく」
「それって、運と同じじゃ?」
「運は、成功者と失敗者が過去を振り返って使う言葉なのよ。途中の者は、使ってはいけない。だから、鍵の生成中、というの」
私は、折り紙を折りながら、眉を上げた。
「鍵のつくり方は、一通りではない。だから、混乱が起こるわ。鍵穴も、一定しない。けど、その鍵と鍵穴が、ちょうどあるべき時に、あるべき姿で当てはまる者がいるのよ。それが、成功者となるわけ」
私は、織り上げた鶴を窓辺に置いた。
「君の鍵は、どんな感じ?」と私は訊ねた。
リスは、難しい顔をした。「わからない。型さえも、まるで定まっていない感じなの。鍵穴は、湯気と同じように、一秒も同じ形を持たない」
胡桃ケーキがやっと運ばれてきた。眼鏡をかけたハリネズミの店員が、両手に2皿持って、丁寧に、一つずつ、自分たちの前に置いた。
胡桃ケーキは、皿に対し、とても小さかった。こじんまりとした三角舟が、白い太平洋に停泊している。船員の胡桃たちは、温められ、溶かされた砂糖によって、がんじがらめにされている。
だれも、どこへも逃げることはできない。
「かわいい」
リスは言って、フォークを手に取った。私は、三角の頂点を切り取って口へ運んだ。
キノコの演奏が終わった。キノコたちは、体を弾ませて、挨拶をする。枝の上のリスも、お辞儀をする。ウサギたちは、キノコに向かって、しきりに話しかけた。木の上のリスは、じっと黙って待っていた。
私たちは、気の向くままに喋り通した。リスは言った。「みんなに、もう七年も会っていない」と。
私は、昔の仲間のことを考えた。森の音楽学校のことを思い返した。学校は小さかったが、先生たちも、自分たち生徒も、同じものを求めていた。
いい音、完璧なテンポ、そして最高の調和を。
「私も、同じ年の子とは、もう何年も会っていないよ」胡桃をつつきながら、私は言った。
すると、リスは、言いずらそうに、こう答えた。
「イタチは、もう、チェロを弾かないんですって」
「本当に?!」
口の中で、ケーキの味がしなくなった。イタチは、チェロの音をこよなく愛していた。先生の言葉に、常に忠実に従っていた。あれほどの努力家はいなかっただろうに。「どうしてさ?」私は訊ねた。
「弾けないんだって。弦を持つと、先生の言葉を思い出すから」
私は、フォークの先っちょで、自分の口元をつついた。
「鍵が、扉を壊したんだ」
「ええ」
「刃物になった」
「ええ」
しばらくして、私たちは、森の館を出た。蟻が、まだあちらこちらを彷徨っていた。どこに食べ物があるか。どこに家があるか。どこに平穏があるか。
「これからどこに行く?」私は訊ねた。
「すぐそこに、公園があったわ。葡萄ジュース屋さんも」
私たちは、胡桃ケーキのことなど、すっかり忘れていた。味さえも、思い出せなかった。頭の中にあるのは、イタチのチェロが葡萄ジュースに溺れ、消える様子だった。
「私、五時には帰らなくちゃ」リスは言った。「キツネに夕飯をつくる予定なの」
「彼氏に何をつくるって?」と私。
「ハンバーグ。彼、ヴィーガンだから、大豆をすり潰して使うの」
「わざわざ?」
「そう。彼の好みだから」
ガチョウが、葡萄ジュースの移動販売をしていた。紫色のぶどうジュースは、手に冷たかった。
二匹は、鈍色に光る湖を眺めた。
私は、泉の手すりで、誰も知らぬ、ある一曲を弾いた。リスは、遠くを見つめ、なにかを考えている。大豆をすり潰す方法。キツネのこと。お金を増やすためにこれからはじめようとしている株のこと。
私も考えている。この曲のおしまいを。この曲の行き先を。誰かに届く夢を。そしてそれが、ただの白昼夢になる現実を。イタチを。チェロを。蟻を。
鍵は再び変形する。私は、まだ、その姿に、怯えていた。