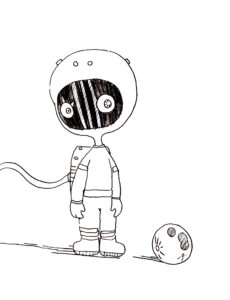秋のある晴れた日のことだった。
僕は、特に背中の痛みのことを気にしていなかった。時に、僕の背中は、雷が下から上へ走ったかのように痛む。けれど、その日は違った。まるで、やわらかな甘栗のように僕の背筋はなめらかで、糸で引っ張られたかのごとくまっすぐ起きられた。
僕の仕事は、本の仕分けだ。だらだらと機械の四角い口から流れてくる本たちが、ベルトコンベヤーにのって流れて来て、それを種類ごとに仕分けていくのだ。
はたして、猫である僕の手が、どれだけこの仕事に必要とされているのか。このことについては、いぜん謎のままだ。僕の仕事は、本を正しい種類に仕分けることであって、なぜ僕がこの仕事を――機械ではなく、生きて間違いを犯す猫である自分が、しかも背中を痛める生きとし生けるものである自分が――しなければいけないのかを考えることではないのだ。
朝早く、ツナのサンドイッチをいそいそと食べて、いつものバス停に向かい、7時32分のいつものバスに乗った。このバスは社員専用のバスで、直接工場へ向かう。停車は、僕の家の近くの公民館前と、北駅だ。そこで大抵の社員を拾い集める。僕ら社員は、出荷前の果物のように、がたがたがたがた揺られて工場へ送られる。
北駅に着いた時、そこそこ親しくしているぶち猫が乗って来た。僕が水田と呼んでいる奴だ。
水田は、僕を見つけたからというわけではなく、ただそこに席が空いていたからだという風に、僕の隣にどかりと座った。水田は細身ではない。立派な脂肪と筋肉が、彼の体を覆っている。それはいつも熱気を発していて、僕の右腕も、すぐに汗ばんだ。
「よお。いい秋晴れだ」
水田は、僕の体の向こうにある窓を覗き見た。透き通るような青空が、くすんだ窓の向こうに広がっている。
「久しぶりに晴れたな」
これが、本日、僕がはじめて口にした言葉だった。
「ずっと雨だった」水田はがらがら言いながら、自分の体で下敷きにしてしまった上着の裾を引っ張った。釦が前で閉じられることはない。
「お前、背中の調子はどうなった?」水田は訊ねてきた。
「それが、今日はとんでもなくいいんだよ!」僕は嬉しくなって、目を大きくさせた。「まるでなにも起こらなかったみたいなんだ!」
「君は、まだ若いからいい。すぐに治る」水田は、眠そうな目をしながら、鼻をずぶずぶ言わせた。「天気がいいからだ」彼は付け足すように言った。
窓の外で、寝坊しがちな太陽が、金色の光を放ちながら建物を照らしはじめた。一台、自転車が窓の下を通った。北駅の方へ向かってゆく。自転車をこぐその猫は、真っ白なシャツに真っ黒なスーツを着て、パソコンバックを肩に下げていた。
空には、雲一つない。ここ数日は雨が続いていたが、その雨がすべてを洗い流してしまったかのようだ。背中の痛みも、それで消えてしまったのだろうか。
工場に着き、僕らはぞろぞろとバスを降りた。更衣室へ行き、作業着に着替える。
水田は、競馬の話をしはじめた。それと、ニュースになっている迷子になった子猫の話をした。
その話は僕も知っていたので、「本当に、心配なことだ」と相槌を打った。それから水田は、外国にいる友人の話をした。青山という名前のその猫は、昨日電話をくれたらしい。「物価が上がってるんだ」水田は言った。
「ツナ缶も、十円高くなったよ」僕は答えた。
「スマイルフード社にしろ。贅沢をいっていられなくなったら、スマイルフード社だ」水田は答えた。
僕は、スマイルフード社のツナ缶は好きではなかった(油が少なくて、ぱさぱさするのだ)が、自分の懐がかつかつなこともわかっていた。僕は、耳をぴくりと動かした。
どちらにせよ、僕らは、生けるしかばねなのだ。工場を縦横無尽に走る、でろでろとしたコンベヤーたち。その上には大量の本が、本が、本が散らばっていて、僕らがまるで飢えた獣のようにかき集めてゆくのを待っている。だが、僕らが飢えているのは、腹ではないのだ。朝食のツナのサンドイッチは、まだ胃袋の中にいる。僕らが飢えているのは――
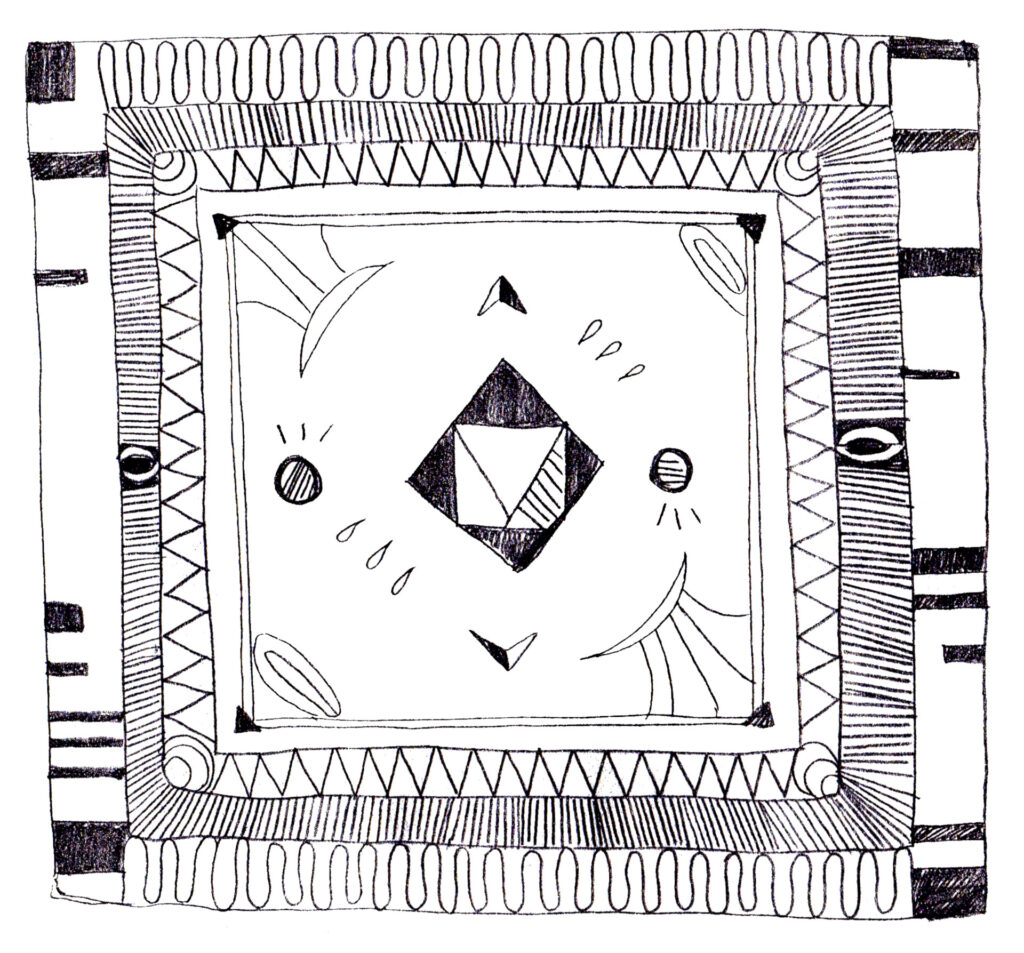
僕らは仕分ける。かつて持ち主がいて、折り目を付けられたけど、丁寧に折り目を伸ばされて、中古書店に並べられた本たち。その本たちが、それでも居場所をなくしてしまうと、ここへやって来るのだ。僕らは、それを仕分けて、また販売に回す。外国の、もっともっと貧しい国へ、新品として売りに出す。背中が取れているもの、表紙が剥がれているもの以外は、綺麗にとっておいて、巨大な倉庫にしまっておくのだ。
僕は、汗水たらして、指定された籠に、雑誌、図鑑、小説、コミックと分けていった。だが、あんまり乱暴に扱うと、工場長が怒鳴ってやって来る。
「おい、こら、11番! 籠の高さ以上に積むのはやめろって言っているだろう。別の籠が上に積めなくなるじゃないか」
工場長は、はつはつ喋る。赤褐色の毛を逆立てて、鉛色の帽子のつばをつまむ。片手には名簿を持って、誰がどの籠をいっぱいにしたのかを記録している。彼の後ろを、猛烈な勢いでフォークリフトが通り過ぎた。いくつもの籠を荷台に積みながら。
工場の中はあまりの騒音なので、僕は工場長の注意に無言で頷くしかなかった。喉がからからだった。汗を何度も拭うが、指先は冷たかった。雑誌の表紙で、指を切った。構わず作業を続けていると、また工場長がやってきて、「11番、お前は血がついた本を買うのか? え?」と、僕がさっき指を切った雑誌をひらひら持ってきて言った。
僕は、はっと顔を上げた。ベルトコンベヤーが止まったのだ。
作業員全員が、僕を見ている。工場長が――背の高い赤褐色が――僕の目をのぞき込んでいる。
そこへ、隣にいた作業員の雌猫が、なにやらポケットをまさぐって、絆創膏を渡してくれた。僕は、静かな工場の中で、みんなに見守られながら、絆創膏を指にまいた。
「作業開始」
とつとつとオペレーターの声がし、ベルトコンベヤーに命が宿った。本たちが、次々と僕の前を横切ってゆく。「僕らが止まったのは、君のせいですよ。僕らのベルトの旅を止めたのは、あなたですよ」そう言いながら、古びた本たちは、古びたため息をついて、通り過ぎてゆく。僕は、折れ曲がった『掃除のhow to本』を破棄籠へ捨てる。胸の中で、安らかな眠りを祈りながら。
午前中、僕は30回、工場の時計を眺めた。15回、水田を探した。水田は、隣の隣のベルトコンベヤーで作業をしていて、その丸い体にむんむんと汗をかいていた。
昼のベルが鳴った。とろとろと流れる一つの川として映っていたベルトコンベヤーは、突如止まって、僕の意識を現実に引き戻した。
二階の食堂は、鉛色の作業服で埋まった。食券を買い、コロッケ定食を水田と食べた。水田は、山瀬というやつとおしゃべりに夢中だった。山瀬は、背が山のように曲がった老人だ。しわしわの口で、コロッケにかぶりつく。髭に、三つ四つ、コロッケの衣がくっつく。
「それ以上も、それ以下でもないよ」山瀬は言った。「ときに、たんとサバが届くでな。明日は妻の命日だ。山向こうの、池の傍でよ、墓参りするんだ。だから、今日、おらは早く上がらしてもらうんだ」
「いつ亡くなったんだっけ?」と水田。水田は、山瀬と長い知り合いらしいのだ。僕がここに来る前から、山瀬はいたし、水田もいたのだから。僕は、山瀬のほとんどを知らない。とてもたれ目だということしか。
「五年前」
山瀬は、汁とコロッケを同時に口に入れて、雫を二三滴こぼした。「費用がかかったよ」
「いくらなんだ」
「葬式に550万。墓に150万だよ」
若い僕は、目をまん丸くした。気づいた山瀬は、苦そうに笑った。
「そう。だから、貯蓄は大事なんじゃて」
「そういえば、ショウガシップの効き目はどうだった?背中の痛みの……」
水田は唐突に訊ね、彼の言葉が終わる前に、山瀬が「ああ!」と叫んだ。「効かなかったよ!」彼は言った。その瞬間、その日初めて、僕は笑い声を漏らした。
午後は、雨が石を穿つよりも、長い長い時間を体感することになる。僕は、これの対策に、ある技を編み出した。それが、「題名つなぎ」だ。
流れてくる本の題名をつなげて、文章をつくる。死の選別をされる本たちにとっても、最後の名誉ある仕事だ。僕の心の中で、名前を呼んでもらえるのだから。心の中で、小さく、密かに。それだけでも、どれだけ価値のあることなのか。
工場長にはわからない、頁の間に挟まれた、本の真実。売店と収入額の数字の中には見つからない、籠にも入らない、本の目的。それを僕は、心の中で鎮魂歌として敬意を示す。
僕は読み上げる。「世界の刃物百科 迫るベートーヴェン 君の胸の中で息絶えて さようならキャンバス! ハムレット あなたの声を聴くために 海に沈む諸島の運命 こわいのはみな同じホップステップジャンプ!! 月収8万の僕が億万長者になれたわけ 鈴木さんちのどんちゃん育児日記 風を追いかけて 緑色の桜 松尾芭蕉のすべて あなたは本当の私だろうか……」
帰りのバスで、僕は背中をさすっていた。水田は、横でぐーすか寝ている。前の猫のスマホ画面が見える。誰かとチャットしている。僕は、外を眺める。絹みたいになめらかな、真っ黒い街を。監視人のように道路を凝視する、信号機の赤い光を。林立する街灯を。駅から去ってゆく、会社員の自転車たちを。
北駅で、水田は降りた。「じゃ、また明日」と言って。僕も、手を一つ上げて応じた。20分後、僕は、朝と同じ、公民館前のバス停で降りた。ここで降りるのは、いつもきまって五人だった。最後の五人、と僕は呼んでいる。ピンクのカーディガンを羽織った中年女性と、タイトジーンズをはいた金色の毛の若い女と、ジャンパーを着た、禿げた中年男、そして短躯な白猫――彼はいつもサングラスをかけてバスを降りた、そして僕だ。
それぞれは、それぞれの住処に向かって散ってゆく。挨拶はほどほどに。頭をわずかに垂れて。カーディガンの猫は、必ず運転手に「お疲れさま!」と親しく述べる。彼女は、ここに勤めて長いのかもしれない。僕も、小さく同じようなことを言う。けれど、背中の痛みが気になってしょうがなくて、7時間立ちっぱなしだった足を引きずりながら、帰途につく。
なめらかな栗の食感を思い起こす。あのようななめらかさが、朝には僕の背中にあったはずだ……そうやって、僕は、朝から昼にあったことを、コンビニへ向かいながら思い返す。
鯖弁当を選んだら、山瀬と、明日命日の奥さんのことが浮かんだ。
風呂の中で、僕は考えた。頭を鎮めると、とたんに静かになった。僕は、700万の海に溺れる夢を見た。700万で、僕は埋められた。誰かが祈りを捧げている。水田だ。水田が、汗をかきながら、必死に本を読み上げている。
「ビックヒストリー超絶科学実験 迷子の滝 知られざる世界の逸話100選 月と六ペンス アラゲイジア 罪と罰 怒りの葡萄 砂の惑星 君死にたまふことなかれ!」
「この700万、もったいないよ」僕は本のがれきの下で、声高に叫ぶ。「君が使うんだ!山瀬さんにショウガシップを作ってあげろよ」
「何千枚もできるな、こりゃ」水田は嬉々として笑う。
「スマイルフード社のツナじゃなくて、ハッピーファミリー社のツナを買いな!添加物がないから」
水田は、重く首を振った。
「だめだ、それじゃやっていけねえ。700万がすぐに終わっちまうさ」
僕の頬を、涙が伝った。
「君はいいやつだよ。だから、ハッピーファミリー、食べてもいいだろう。君はそうする価値があるやつさ」
「いいや、違う。それじゃ生きていけねえんだよ、黒崎。若いから、知らないだろうがな」
工場長がやってきた。「11番!仕事に戻るんだ。また血のついた本があるぞ」と言いながら。彼は、僕を一瞬見下ろすと、「次はおなじ間違いを犯すなよ」と言って、最後の本を僕の顔に投げ、僕を完全に埋めた。
闇の中で、僕は唱えた。
「ファウスト 神曲 氷の心臓 一番シンプルな世界史 我々はどこへいくのか 僕の……