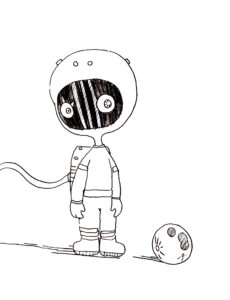その家は、海の上にあった。赤い屋根の、小さな家。白い窓枠が一階と二階に小ぢんまりとついていて、車二台は停められそうな庭があり、注ぐ日の光は、いつもどこか静寂に満ちていた。
しかし、気分屋な海の嵐は、悪びれる風もなく、家の窓をいたずらに叩きつけ、定期的に訪れる潮は、車どころか芝さえも、庭にとどまることを許さなかった。小さな家の運命は、すべて海に委ねられていた。お天気の日も嵐の日も、家は、黙ってそこに留まり続けるしかなかった。
そんな家に住むのは、一人のしがない男だった。男は、たびたび満ちる潮のせいで黒くなった木の板の庭を、いつも丹念に磨いていた。彼は、この黒ずみや読めない風のことを害悪であるとはちっとも思わず、ただ起きたことを受け入れ、淡々と過ごしていた。満潮の時期になると家の中に閉じこもり、潮が引くのを、月を眺めて待った。家の中で、他に雨漏りや傷んだところが見つかれば、丁寧に直した。そうして、一年に一度は、必ず、家の屋根を真っ赤に塗り直すのだった。
彼が使う工具やペンキなどは、通りすがりの舟乗りたちが持ってきた。男と交流をするのは、たいていは彼らだけで、よって、この男のことを知るのは、ほとんど彼らしかいなかった。
舟乗りたちは、漁を終え、帰りのついでに男の家に寄り、必要なものを伺った。それは取り決めではなく、男が頼んだことでもなく、舟乗りたちの意思だった。
「なんであんな男のことを、それほど気にかけるのさ」
一人の舟乗りの妻は、そう言って主人に突っかかった。果物なり小麦粉なりを、主人に言われたとおり紙袋に詰めていたのだが、本当は家にこんな余裕はなく、不機嫌になっていた。子どもが四人もいたし、漁師である夫の稼ぎも、さほどよくなかった。
しかし、舟乗りの夫は、こう言うのみだった。
「俺たちは、対価を払っているんだ。なにもせずに通り過ぎるなんて、不可能だよ。あの男は、この果物、小麦粉以上のものをくれるんだから」
妻は肩をすくめ、町の魚処理所へ出稼ぎに行った。子どもたちがやって来て、舟乗りの周りを走り、「今日はいつ帰って来るの?」と飛び跳ねた。
「いい子だから、静かに待っているんだ。日が沈むころに帰って来るから」
「あの家のところに行くんだね?」抱え上げられた末っ子の男の子が言った。
舟乗りは、はっきり頷くことはしなかったが、「彼にお前のことを伝えよう」と言った。
「きっと覚えてくるのよ!」二番目の少女が、ませた様子で、腰に手を当てて言った。
「お願いだから、聞きたいの」と一番上の少女が次女の肩を掴んで言う。
「ああ、今度こそ。今度こそだ」
舟乗りはそう言って、しっかり網を掴んで家を出ていくのだが、そんな彼を、三番目の子どもである長男は、大きな鼻をこすり、腕を組んで見つめるのだった。
「きっと、また無理だぜ。一つの音も覚えてられないよ。誰一人、覚えて帰ったやつなんていないんだから」
舟乗りは、仲間たちと合流し、その日も一日中、海と魚とを相手に戦った。
空が熟れた杏子色になり、滲む紫色の雲が夜を運びはじめるころ。彼ら漁師たちは、魚で舟を少しだけ重くさせ、家へ向かって櫂をこいだ。
海の男たちは、無言だった。波と潮風が、彼らの髭や髪を掴んで撫でて、べっとりと、塩辛い海の証を残した。
彼らは、疲労で叫ぶ筋肉を無情に動かし、島と家と子どものことだけを考えるようにした。
けれど、それを妨げるものが一つあった。島と男たちの間に、あの赤い屋根の家があったのだ。男たちは毎度、「今日は声をかけるだけにしよう」と思うのだが、家の影が夕闇の中で大きくなるにつれ、櫂を漕ぐ手が遅くなり、結局、だれか一人が言うのだった。
「今日も、あれを聞いていこうじゃないか。少しでもさ」
みんなは、先ほどの決心に苛まれながら、とうとう彼の言葉に賛成し、櫂をぴったり止めるのだった。
「少しだ。遅くなっては困る。少しだからな」
顎鬚をたっぷり生やした一人の漁師は、仲間に、それに自分にも言い聞かせるように、強く述べた。仲間たちは、それに慇懃に頷いた。
顎鬚漁師と数人の仲間は、家へ向かって静かに舟を操り、他の仲間は、慌ただしく、男への贈り物の準備をした。
その日、赤い屋根の家の男は、桟橋に腰掛け、釣り糸をたらしていた。もうすっかりあたりは暗くなり、手元も見えづらくなっていたので、彼は小さな魚一匹が入ったバケツを持って、家へ戻るところだった。
「こんばんは! 調子はどうだい!」
髭男が、お決まりの文句を男に投げた。
家に向かいかけていた男は、すっと振り返り、バケツを丁寧な動作で置いて、手を挙げた。これが、男によるいつもの返事だった。
漁師たちは舟を近づけ、今日はなにを持ってきたか、男へ語るべく、桟橋へ立った。
「蝋燭、燐寸、リンゴ、タラの燻製、瓜、じゃがいも、たばこと少しの酒も」
髭男が静かに説明する間、他の男たちは、せっせと桟橋に贈り物を降ろした。
家の男は、それらに目を丸くし、首を横に振った。そこを、髭男がとどめた。
「いやいや、受け取ってもらわなければならん。あんたは、その価値がある人だ」
男は、なおも首を振ろうとした。そして、自分のバケツを指し、魚一匹しかいないことを示した。
「違うんですよ。俺たちは、好きであんたにこれを持ってきているんです。俺たちが、なにかをもらう必要はねえ」鼻の詰まった漁師が言った。
「……ただ、あの曲の恩返しなんですよ。息子もそう望んでいてさ」四人の子どもをもつあの男が、控えめに、希望を滲ませて言った。
海の家の男は、暗がりでへりくだる漁師たちをまじまじ見つめ、やがて手を動かし、なにかを示した。
その動きの意味を、漁師たちは知らなかったが、男が何度も漁師たちより下に頭を下げるので、彼らは、「じゃあ、本日も聞かせてくれるんだな?」と勝手に喜び、やんややんやと舟に飛び乗った。
「待ってるぞ!」
漁師たちは手をさすり、さっそく櫂を手に取った。そして、家の裏側へと回っていった。
家の男は、贈り物をしっかり抱え上げると、家に入り、扉を閉めた。
海で待つ漁師たちは、耳を澄ませた。波音の合間にやってくるであろうあの曲のはじまりの音を、探り出そうとした。自分の息の音も煩わしいほどだ。鼻声の男が鼻水をすすると、「黙れ黙れ」と髭男が言った。
どれくらい時間が経っただろう。一番星を追いかけて、二つ三つと星々が輝きはじめたとき、あの曲が聞こえた。
波に混じって、ゆらゆらと、ころころと、ピアノによるかすかな調べが、漁師たちの耳をくすぐった。やがてその音楽は、彼らの舟を包み、髭や髪の毛を浮かび上がらせ、獲った魚を銀色に輝かせた。
漁師たちは、月がいっそう明るく光るのを見た。海が男の家を楽し気に洗い、手を伸ばすがごとく、波が桟橋に打ち寄せた。
男たちはそれから、風が頭の後ろを駆け抜けるのを感じた。風は海を誘い、海はそれに応じて、いくつもの水球を上空へ浮かばせた。魚が泳ぎ、星が散るその球体を、男たちは息を飲んで見守った。紺色に揺らぐその球体は、遠くの星々を大きく見せ、煌めく星たちは、中で七色に輝いた。その合間を、海の住人—魚、ヒトデ、サメ、海藻が、夢のように泳いでいるのだ。
男たちが、詰めた息を再び吐いた時、すっかり海はもとの轟きを響かせて、自分たちはゆらゆらとその手の平で遊ばれていた。漆黒のしょっぱい海の上を。
鼻づまり男に限らず、みなが鼻を啜った。帽子を取り、胸に抱いた。顎鬚男は、目頭をつまんでこすった。
「……さあ、もう行こうや」
彼らは、厳かに櫂をとり、家路をたどった。彼らは、長い間、荘厳な静寂の中にいた。
だから、あの子持ちの漁師が、「それで、どうだったの? ちゃんと覚えてきた?」と家に帰って子どもたちに訊ねられた時には、はっとして我に帰るのだった。
「……ああ、しまった!」
「ほらみろ」鼻の大きな長男が、鼻の穴を膨らませて、苛立たし気に言った。「僕は確かめたさ。どの漁師も、覚えていないぜ。父ちゃんが覚えられるわけないさ。あの男が弾く曲なんて」
そんな漁師たちが獲った魚を食べた、とある住人は、「馬鹿みたいだ」と述べた。
「なにがだ」
そう訊ねたのは、小さな料理屋を営む店主だった。彼は、いましがた、質素なタラのムニエルを、目の前の男に出したところだった。
ムニエルを食したのは、小綺麗な茶色のスーツをまとう紳士だった。彼は、最近この町へ越して来たばかりの新参者だった。いつも悪態ばかりついているが、身なりが上品であるので、町の者は近づきもせず、追い出したりもしない、曖昧な関係を築いていた。
その紳士が、口を歪めて言うのだ。
「このタラ。こいつだけ、口の中で消えてしまう。いったい、お前はなにをしたんだ?」
「塩とレモンで焼いただけだ」
「馬鹿め。それでこれほど上等な味になるわけがない」
そこで紳士は、すぐさまタラに問題があるとみた。「こいつは、どこで獲っているんだ」
「そこの海だ。見えるだろう。あの窓の向こうにある海だよ。俺の昔からの友人たちが獲っているんだ」
紳士は、なんの変哲もない、鉄色の海を振り返った。
「じゃがいもは青臭く、豚肉は反吐同然となり、パンにはカビが生えるこの街で、なぜお前の店のタラがこれほど美味くなるんだ? え?」
店の主人は、この紳士が誉め言葉を述べることの方に驚いていたので、タラよりも紳士がおかしいのだと思った。
「俺は、焼いて味をつけただけだ。まあ……礼は受け取っておくよ」
店の主人がはにかんで汗を拭っている間に、紳士は鼻を鳴らして立ち去った。綺麗にタラだけを食べ終えて。
紳士は、ぱりっと音がしそうなスーツの前裾を引っ張り、その姿を住人に見せつけるがごとく颯爽と歩きながら、目を爛々と光らせた。そして、広場で遊ぶ子どもらを見つけると、すかさず声をかけた。
「漁師はどこにいる。あの店のタラを仕留めている漁師は、いったいどこだ」
「僕の父さんだよ」
ボールを持った鼻の大きな少年が、目を細めて言った。
「案内しろ」
少年は、上等なスーツを着る紳士にまさか頼みごとをされるとは思わなかったので、驚きながら小さく肩をすくめ、自分の家へ向かった。
さざ波の歌が絶えず聞こえる、傾いだ薄汚い小屋へ、紳士は少年に案内された。
紳士は、一つ鼻をつまんで引っ張った。「最高だ」彼は皮肉をこめて言った。
少年は、開け放たれた玄関から母親を呼んだ。しかし、彼女が出てくる前に、紳士はずかずかと入りこんだ。
「まあ、なに!?」
「タラを獲る男は、どこにいる」
「この町の男は、ほとんどタラを獲るよ」母親は、スーツの男を睨み上げた。「うちの主人になんの用?」
「どこにいる」
「こっちの質問に答えなさいよ。ここはあたしらの家だよ!」
スーツの男は舌打ちをして、入った時と同様、ずかずかと出て行った。
母親は、荒々しさを放つその背中に、刺すように告げた。
「漁師は、海にしかいないこと、知ってるでしょ!」
島の港にやって来た紳士は、遠くの沖で漁をする舟を見つけた。それから鼻を鳴らすと、塩漬け用の樽の上に座った。
そうして、日が暮れて月が昇るころ、漁師たちが桟橋に戻ってくると、彼は立ち上がった。
「どこでタラを獲った」
漁師たちは、月光にぼんやり浮かぶ背格好で、それが町のおかしな紳士だと気がついた。
彼らは会話をしようか迷ったが、一番に顎髭男が進み出た。
「そりゃ、日によって変わるもんだ。獲れるかどうかは、海しか知らねえ。俺たちは、それに従うだけだ」
「お前たちは、帰りにあの家へ寄ったな。なぜだ?」
紳士の男は、しっかりと見ていた。海の真ん中に浮かぶ、あの奇妙な家に、舟が近づいていくところを。
漁師たちは、そこで、みんな無言になった。
「あそこに、なにかあるんだな?」紳士は鋭かった。
顎髭男は、息を吸った。
「一人の唖者がいる。それだけだ」
「なぜ、漁の最後に向かうんだ?」
「お前には関係のないことだ」
その日は、それで終わった。漁師たちは紳士を取り残し、そそくさと家へ帰った。紳士は、だが、朝が来るまで、じっと赤い屋根の家を見つめた。
あくる日、紳士は、漁師たちに同行を申し出た。どちらかというと、命令に近かったのだが。漁師たちは、もちろん、気が乗らなかった。
「舟は、よそ者を嫌うぜ? 海もそれに気づく。とたんにあんたも俺たちも、海のもずくとなる。お陀仏よ」
「あの家で降ろせばいい。そのあと、お前たちはタラを獲っていればいいだろう」
なかば強引なかたちで、漁師たちは舟に乗せられ、紳士を赤い家へ送ることになった。顎鬚男は、胸騒ぎがしてならず、天と海に祈りを捧げた。
漁師たちは、無言で紳士を家の桟橋に降ろした。そして、心の中で謝罪をしながら、家を離れるのだった。
一方紳士は、ぎらりと家を振り返り、その秘密を見つけ出そうと、燃えていた。
彼は、つかつかと戸口に近づくと、力強く拳で叩いた。
「おい、おい! 答えることができなくとも、この扉を開けることはできるだろう。おい、出てこないか!」
すると、頭上でかたんと音がした。
見上げると、一人の男が、海鳥のごとく屋根に居座り、こちらを見下ろしていた。修繕のためか、片手に金づちが握られている。
「降りてこい。貴様に話がある」紳士は、大きく腕を振り下ろした。
男は、金槌を置いて手を挙げると、しばらくして、家の裏側から姿を現した。
紳士は、唖の男とそこではじめて対面した。唖の男の方も、同じだった。
唖の男は、強い眉毛と柔らかな瞳をもった、四十ほどの人だった。肌は日に焼け、太くはないががっしりと筋肉が張った四肢を持ち、整えられた口髭と顎髭は、誠実さを感じさせた。
唖の男の方でも、紳士をとくと見つめていた。良質な土色のスーツに、青空色のネクタイ。袖口や裾は海水に濡れていたものの、背筋はすっくと伸びて精悍な感じがし、町の者とどこか一線を画していた。魅力的なのはその瞳で、内側から燃え立つ興味と、謎を捉えられない苛立ちで、燦然と光っていた。
二人の男は、黙って相手を観察した。そうして先に動いたのは、やはりスーツの男だった。
「貴様は、ここでなにをしている」
彼は、唖者に迫った。「こんな海の上で、世捨て人のように過ごして。ここに貴様の求めるものがあるというのか。貴様はこの町の者ではないな? わかるぞ。俺がそうだからな」
唖の男はたじろいだが、ぐっと胸を反らして一歩も引かなかった。
「口が利けないのが惜しいが、貴様には、きっと、ここにいる理由などないはずだ。その目の中に、俺と同じ炎がある。言わなくともわかるほどの炎だ。そいつをもつ人間は、こんなところでのうのうと生きてはならぬ。貴様も、それを理解しているはず。……さあ、教えろっ。貴様は、その炎をもって、ここでなにをする必要があるがあるのだ?!」
突然、唖者は紳士を突き飛ばすと、家の中へ駆けこんだ。紳士は、危うく海に転がり落ちるところだったが、なんとか桟橋にへばりついた。
「待てっ!」
這って立ち上がると、紳士は駆け出し、閉じられたばかりの戸にぶつかった。それから、慌てて取っ手を引き、戸を開けた。
階段を駆け上がる唖者の姿があった。紳士は唸ったが、一度だけ、家の中をぐるりと睨めつけた。
質素な食事台と椅子が右にあり、左手には、簡易な台所があった。真正面には、左へ曲がって消えていく階段がある。
紳士は、足を鳴らしてその階段を上がった。途中の窓から、いやに青い海が見えた。
波の音がこだまする家で、紳士は、向かい合う二つの部屋に鉢合わせた。その片方に、ピアノを前にして背を向ける、あの唖者を見つけた。
紳士は、一歩部屋へ入り込んだ。箪笥、窓、そしてピアノ。寝台は向かいの部屋にあり、このピアノの部屋には、暮らしの気配というものがまったくなかった。彩りと言えば、箪笥の上に置かれた、小さな花の群れだけだった。
海の上で花を愛でるなど、唖者は贅沢をしていると、紳士は思った。わざわざ取り寄せて、塩辛い海のど真ん中に飾っているというのか。
「馬鹿め」紳士は、口癖を唖者に放った。「これが、花が、ピアノが、貴様の秘密か。貴様の神聖かっ」
唖者の男は、振り返った。眉を吊り上げ、紳士をまじまじと見つめる。そして、いきなり椅子に腰かけると、鍵盤に手を滑らせた。
唖者の指は、根のように鍵盤の上に広がり、獣のように走り、飛び、着地しては、また別の場所へ飛んだ。かと思いきや、風が指と鍵盤に吹き、雷鳴が足を支配し、耳と目を、炎が包んだ。
紳士の顔に、大風が押し寄せた。それは雨を運び、たっぷりとした雫をぶつけてきた。数多の植物が繁茂し、紳士は、赤々と燃える演奏者めがけて、かき分け、進むしかなかった。
炎の男が端から端へ鍵盤をたたいた時、紳士の手とぶつかった。紳士は、瞳をぎらつかせ、唖者を睨みながら、次の音、次の音を叩いた。
二人の男は、鍵盤の上でせめぎ合った。ごうごうと風が鳴り、雨が降り、足元で波のしぶきが上がり、木の枝が、天井をめきめきと押し上げた。
彼らは、音を生み出しながら、額をぶつけ、互いの目の中を見やった。渦巻く虹彩の、その奥を。
そこで紳士は、唖の中に、待ち焦がれる愛を見た。抱き合う二人の男を見た。育んだ小さな命二つを見た。黒々とした炎が彼らを包み、砲弾の雨が降り注ぐのを見た。慟哭する一人の物言わぬ男を見た。
唖者は唖者で、紳士の中に、天空の青を見た。煌々と輝く太陽と、鋭く照る銀の機体を見つけた。操縦桿を握る拳を見た。異国へ送られる姉妹を見た。彼女たちを買い取るために商売をするスーツ姿の男を見た。死亡証明書を眺める男を見た。
気づけば二人は、荒々しい顔をして、向かい合って立っていた。額に汗が浮き、演奏後の残響が、耳に痛くささった。
紳士は、部屋を出て行った。
唖者が一階へ降りたとき、食事台の席に、紳士が無言で座っていた。彼は、手を前に組み、横の窓を見ていた。
唖者が近づくと、彼の目は、しっかりと、沈黙する男を捉えた。唖者の手には、真っ赤なアネモネがあった。
紳士は、黙って受け取った。
「俺は、ここを出て行こう。この町をだ」紳士は言った。「ここには、なにもない。商売もできん。あるとすれば、舌でとけるタラだけだ」
唖者は、食事台に腰かけ、紳士を見下ろした。紳士の目の中の炎は、静かなものだった。
「生命を弾く者は、一人で充分だ。タラを味わうのも、一人で充分だ。だが、俺は、その両方から降りよう」
彼は、その深い目を唖者に向けた。
「一つ聞かせてくれ。貴様は、永遠に弾き続けるのだろう。死んでもなお。だが、貴様の悲愴を祈りへと解放させるその炎は、いったいなんなのか?」
唖者は、首を少し傾け、窓を示した。
最後の輝きを放つ夕陽を背に、漁師たちの舟が、小さな虫のように浮かんでいた。
紳士は、それを認めると、胸ポケットにアネモネを丁寧に入れた。そして、仰々しく立ち上がり、唖者の肩に触れた。とたん、火花が一瞬、ばちっと燃え上がり、一陣の風が吹いた。
「ン」
唖者は、その手を掴んで、頷いた。
桃色に光る満月が、水平線近くに浮いていた。その手前で、彼らは影となり、別れを交わした。
「さらばだ、戦下の敵、人間の友。もう二度と、会うことはないだろう」
紳士は去った。唖者は、満月によって導かれる潮が桟橋を沈ませるまで、黙って彼を見送り続けた。
唖者の男は、毎晩弾き続けた。漁師に頼まれても、頼まれなくとも。指が鍵盤で踊る。波が喜び、真っ赤なアネモネが、涙を流して散ってゆく。
彼は、弾いた。愛した人の血、赤ん坊の笑い、姉妹が流した涙。それらを運んで湛えた、海のために。
タラが泳ぐ。漁師が捕らえる。待ち続ける幼い命が、それらを再び飲み、腹に収める。
燃えるアネモネは、遠く離れた国にある、寂れた墓所でも見つかった。そこへ最後に立ち寄ったのは、茶のスーツを着た紳士だった。
彼は、その真っ赤な花をたむけると、墓石の上で、あの曲を弾いた。
音はなかったものの、あの曲を口ずさむ紳士の声は、わびしい墓所で響いていた。
彼は、一拍一音、忘れることなどなかった。