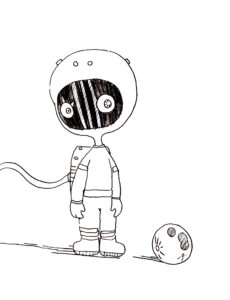私の傍に左手がいる。くすんだ水色。布団のそばを徘徊している。手首には桃色のビーズのブレスレットをしている。
左手は、五本の指を足として使い、フローリングの床を這いまわる。
私は、その左手をずっと見つめる。左手は、早起きである。
目が覚めると、左手は、必ずいまのように動き回っている。なにかを探しているでもなく、怯えている訳でも、楽しんでいるわけでもない。ただ義務であるかのように、行ったり来たりを繰り返しているのだ。
私は、そんな左手に話しかけたりはしない。耳がないから、そもそも意味がない、というわけでは、決してない。
左手は、自由な自分の時間を過ごしているのだ。朝の静寂に含まれた、あの個人的な時間を。そして私も、目覚めたばかりの、甘く、重い時間を過ごしている。この時間は、だれもだれかに干渉する権利はない。私たちは、その決まりを守れる仲なのだ。
左手は、私の足元の方へ行き、手首を床につけて休むと、今度は五本の指足で、屈伸運動をし始めた。
私は、頭だけを起こして、左手の屈伸をながめた。手首の切り口は、硝子のようになめらかで、カーテン越しに滲む朝日をぼんやり反射した。
私は掛布団を剥ぎ、音を立てず起き上がった。左手は、相変わらず屈伸している。ラジオ体操とでも言わんばかりに。その運動は、一人の人間が起き上がっただけではやめるわけがない、というように、私のことを左手は無視する。
だから私は、左手をそっと持ち上げた。生身の人間と同じ重み、暖かさ、柔らかさを感じる。左手は、私の手の中で、一度、ふっと力を抜いて身をゆだねた。わずかに骨ばり、だけれど、ちょうど良い厚みと、筋肉、若いようで、様々な動作をしてきたがゆえのたくましさと繊細さを持つ左手は、さっきの運動をやめて、ただじっとしていた。
私は、そのまま台所へ行った。左手はテーブルに置いておいて、我慢ならない渇きのために水を飲んだ。
左手は、まるでそこが未踏の地であるかのように、テーブルの上をせわしなく動き回った。その様子を傍目に、私は冷蔵庫から6Pチーズを取り出して、朝ごはんにした。
左手を前に、アルミをはぐ。チーズの頂点を齧りながら、右へ左へと這いまわる左手を見る。
もう一度横切った時、私は、左手を押して、ごろんと転がした。
いたずらごころが、つい芽生えた。だが、左手は叫びやしなかった。なんたって、左手だから。
ひっくり返った左手は、起き上がろうとする虫みたいに、指を細かく動かした。ブレスレットが、テーブルに当たって、カチャカチャ音を立てる。
私は、チーズを食べ終えると、転がしてしまったお詫びに、左手の手のひらに、新しい6Pチーズを置いてあげた。
ひんやりとした三角のチーズは、左手の動きを止めた。左手は、数秒間、じっとそのままだった。
それから、実に器用に、五本の指で手の平のものを持ち上げた。
水色の指の間で、チーズは静止した。カーテンの引かれた、薄暗い居間で、それはまるで優勝杯のように、唯一無二で、優美な力を持っていた。
左手は、チーズの扱いを知っているのだろうか。目がなくとも、その柔らかさに気づいて、決して潰しはしない、破壊と観察を、この手は知っているのだろうか? あの難しい二つの動作を。
私は、時計を見上げた。7時13分を指していた。私は、仕事のために着替え始めた。
バスの中で、私は、運転手の耳の後ろを、斜め後ろの、最後尾から二列目の席に座りながら眺めている。白髪の混じった髪の毛、切りそろえられた襟足を、バックの中にいる左手のことを気にしながら眺めている。
五つほどバス停を通りすぎると、図書館前に着く。そこで、私の知っている顔が入って来る。学生の頃から知る顔が。
彼は、私を見つけると、少し頷いてやって来る。この頷きの瞬間が、私と彼との約束だ。
彼は頷き、私は席を詰める。そうすることを許す。彼に。私自身に。
「昨日は、何時に寝たと思う?」彼が問う。まるで、会話の続きみたいに。
「寝ていない」私は答える。左手の入ったカバンを、ぐっと引き寄せ、抱く。
「ああ。ゼルダのせいじゃねえぜ? エーペックスでもねえ。そして、酒でもねえ」
彼は大まじめに頷く。前の背もたれにある取っ手を、ジェットコースターを乗る時のように掴んで、しっかり前を向く。
「ありえない」私は言う。少し笑って。
彼は、しばらく沈黙する。それもあり得ないこと。だから、あたしはもう一度笑って言う。「ありえない」と。窓を見る。
彼は、生え際を掻いたあと、後ろの背もたれに背を預け、小さく息を吐いた。
「やばいものを拾ったからだよ」
聞き取れないほど小さく、彼は言った。
「え、なに?」と私。鞄の底を掴むようにして抱く。
「バス、降りたら話す」彼は言った。
右に行くと工場、左に行けば出版社がある。私は右へ。彼は左へ足を向ける。いつもなら。そう、いつもなら。
その日は、どちらも左右に別れなかった。彼がこう言ったからだ。
「手の死体を見つけたんだ」
私の頭の中心から足先までを、電撃が一直線に走った。
彼は、眉の下を黒々とさせて、険しい顔になって言った。
「なあ、なあ、信じてくれ。しかも、それ、動いていたんだ」
「夢でしょう、いつも通り。前は、エンダーマンが枕元に立って、起き上がることができなかったって言ってたじゃん」
言いながら私は、鞄を彼と反対側へかけなおした。
「ちがうちがうちがう。本物の手だ。手首ちょい上から切り取られてる、動く手だ。お、お、お、俺、ビニール袋に入れて、燃えるゴミに出そうと思ったんだけど、今日、ペットボトルの日だろ? だから、まだそのまま家にいるんだよ」彼は、私の二の腕あたりを掴んだ。
「どこで拾ったの。なんで拾ったの」
「昨日の夜、帰りに。会社の外に落ちていたんだ」
彼は、マネキンの腕だと思ったと言った。向かいに婦人服屋があるから、と。
だから、届けに行くことにした。そうやって拾い上げたとき、なかなか肉的なものを感じたという。
「手を握った感じがしたんだ。そこで捨てればよかったんだけど……」
喋り通していた彼は、そこで躊躇った。
「だけど?」と私。
「……いいや。とにかく持ち帰って、確認することにしたんだ。でも、違った。マネキンじゃねえ。あれは……「人間」だ。俺、一睡もしないで、今日は出てきたよ」
最期、彼はてきとうに締めくくった。まるで、真意を隠すかのように。
時刻が迫っていた。私は腕時計を見て、彼もスマホの画面を見た。
「なあ、今日、確認しにきてくれないか? 警察に言おうか、悩んでるんだ」
「ロボットよ」私は工場の方へ足を向けながら言った。「それか、義手かもしれないね。警察に届けた方がいいよ」
「あ、うん」
私たちは、小さく手を挙げて、それぞれの仕事へ向かった。
そうしながら私は、鞄の中へ、そっと手を滑り込ませた。
左手は、指先を握ってきた。
朝礼に出ても、ラジオ体操をしても、ピッキングをしても、食堂で昼食を食べても、頭から離れない。
鍵つきロッカーに入れた鞄。その中にいる左手のことが。
タイムカードを打って、帰宅する。ロッカーを開けたあと、私は同じ派遣元の人と、どこの会社が一番時給が高いか話をして、手を鞄に滑り込ませる。
左手がいる。少し力が抜けていたところを、私の指がやってきたことで、また息を吹き返す。左手は、静かに私の手を握る。
私は、いつものバス停へ向かわず、駅へ行くバス停へ、歩いて向かった。
駅内の複合施設で夕飯を食べ、映画を見て、ささやかな量の食品を買った。
そして、最終便のバスで、帰宅した。
シャワーを浴びながら、テーブルに放した左手のことを考える。映画の中で、ずっと握っていたあの左手を。スクリーンの中の人々は、同じように、互いに手を握り、笑い、食事し、涙し、窮地から相手を救いあげていた。
風呂から上がると、テーブルの上で、左手は、小指から人差し指という順番で、指を卓に当て、軽快な音を出していた。
私は、その手を見下ろしながら、そっと甲に触れた。指の動きは止まった。
床の布団に寝そべる。触れている。手の中に、手が。左手は、私の頬を包む。それを枕にして、私は目を閉じる。眼窩の下を、左手はなぜる。親指で。そこにいることを、記すように。
(2023)