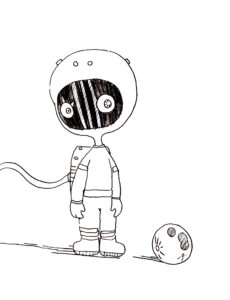東の海岸で、老人が一人座っている。肌は青みがかった灰色。彼は岩の一つに腰かけ、背後からの波の音を聞いている。
老人の目は、腐った豆のように皴だらけで、膨らんでいる。
老人は、目が見えない。波の音だけが、彼の世界のすべてなのだ。
老人の足元に、頭のなくなった蛇がいる。ちょうど齧られたあとなのか、鮮紅の血と桃色の肉が太陽に輝いている。
老人は、口を湿した。塩の味がした。彼はそのうち、細いが、確かに響く澄んだ声で、歌を歌い始めた。
なにもない朝に
紺色の壁が見える
浮かぶのは 春先の山々だけ
君らがかつて連れて行ってくれた
あの山だけ
嘘が俺を迎えにきた
けれど これでもう終わり
嘘も俺も
紺の壁に閉ざされたまま
生命の液が
首から流れ出るのを感じる
けれどまだ
海の傍で 君らを待つ
すると、尻の下の岩が、わずかに動いた。
老人は、尻をずらすようにして立ち上がった。
「カメだったか」
その通り、岩はのっそり長い首を出し、下から四つの足を出した。老人にその様子は見えなかったが、砂浜を何かが動く音で、そうだろうと理解した。
カメは、老人と違って、海の方をまっすぐ見て歩きだした。
「どこへ行くのだ?」
老人は問いかけた。答えは望んでいなかったものの、どこからか声がした。
「帰らなくちゃいけないのです。元の家に」
老人は、じっと黙って、声がした方のことを考えた。そして言った。
「もしや、君―カメが喋ったのかね」
「そうですね」
カメは先ほどよりも進んだらしい。声が遠くから聞こえる。
老人は、一歩進んで、声を上げた。
「私の歌が気に食わなかったから帰るのか? まあそれでもいいが。あまり気分がいいものではないからな。教えてくれ! 去るのは私の歌が原因か!? それとも、重くのしかかっていたものから去りたかっただけなのか!?」
カメは、遠くからこう答えた。
「いいえ。あなたの歌は関係ありません。重さのことも。なにもかも。ただ、家の場所を思い出したのです。ただそれだけのことです!」
老人は、フケの散った顎鬚を撫でた。
「ど忘れ迷子のカメ岩だった、というわけか」
老人の独り言は、風に乗って飛ばされた。
老人は、蛇の死骸を探り当て、むんずとつかむと、奇声を発して振り回し、カメの方へ走りだした。
「なんでしょう?」
カメは、ぽつり言ったが、振り返ることはしなかった。その時間を要するのでさえ躊躇われるほど、帰ることに夢中だった。
老人は、泡を吹きながら駆けていた。
「私も連れていけ‼逃がす者か!私も連れていけ!」
だが老人は、カメの甲羅に蹴躓いた。砂浜にべったり投げ出される。
カメは、片方の目でそれを認めたが、立ち止まりはしなかった
「急いでいるんです。私、急いでいるんで」
だが、老人は砂を吐きだし、立ち上がると、蛇でそこら中を叩いた。
「愚か者が! ええい、愚かものが! 君は喋らぬ亀であった方がよっぽどよかった。岩であった方がよっぽどよかった!」
「おかしなおじいさんだ」カメは歩きながら言った。
「なに!? お前の方がよっぽどおかしい。言葉を話すんだからな!」
カメは、蛇を振り回す老人から、なるべく急いで逃げた。「言っておきますけど、海もそういい所ではありませんよ」
「知っている!」老人は、てんで違う方向に向かって喚いた。
「全部、紺色の壁なんです。光などありはしない。かき分ける水には、だれかのおしっこと、うんちと、血と、羊水がまじっている。生きているものと死んでいるものの欠片が、ごた混ぜになっているんですよ。まったく、息苦しいったらない」
「そこに、私の待っている者がいるのだ!」
老人は、カメを見つけたようだった。蛇を浜に叩きつけながら、ゆっくりカメに近づいていく。
カメは、もう波打ち際まで来ていた。湿った地面が、ヒレや甲羅の裏を冷やす。
「おじいさん。あなたは陸の生き物でしょう。海の底に、あなたが望むものはいませんよ。魚が食べたいというのなら別ですけれど」
カメは、飛んできた水飛沫に目をしばたかせた。すると、甲羅に何かが触れた
老人の手だった。
「お願いだ、連れていってくれ。ここでどれほど待っていても、やって来ないんだ。だから、こっちから行くしかないのだ。さあ、連れて行っておくれ」
カメは、ぶるぶると震えながら、首を伸ばした。
「それほど行きたいなら、勝手に行けばいい。私の記憶を探る道を、どうかじゃましないでください。せっかく思い出したところなのに」
カメは、ヒレと後ろ脚で、力いっぱい海へ向かった。老人は、甲羅に爪を立てて、しっかりへばりついた。
一匹と一人は、しばらくずりずりと、ともに歩いた。
「しつこいなあ! だれかあ! 助けてくれえ!」カメはとうとう叫んだ。
「まったく、もういい。いくじなしのぼけカメめ。私は自分で行く!」
「さっきからそうしろと言っているじゃないか」
そう言うカメの脇を、老人は、のしのし海へと向かって歩いた。
「あいつらが待っているのだ。あいつらが待っているのだ」
老人は、波が手を差し伸べる一歩手前で立ち止まった。そして、くるりと振り返った。
「私をその冷たい潮の腕で抱け! そしてあいつらに再び合わせるのだ!」
老人は、ざっぷり背中から海へ飛び込んだ。
「哀れな老人だ」
カメは首を振って、せかせかと、波へあたりにいった。
カメはひんやりとしたしょっぱい水に目を閉じ、思わず歌を歌った。
君は闇の手 光の手
その両の手で僕を抱く
いまいましい生命の力
君の奥底の秘密は 誰も知らぬ
僕はその秘密を避け
もと居た場所に帰るだけ
ふるさとの 命たぎる紺の世界に
そのとき、一番大きな波がやってきた。カメの体は掬われ、海の懐へとひきずられた。
カメは目をつむったまま、思い出した家路を頭に描いた。ひれをひとかき、ふたかき、重い甲羅とともに、鳥のように羽ばたく。泡立つ水が、顔を洗う。
そうしてカメは、海の腕に抱えられて、静かに潜水していくのだった。
そのかたわら、凶暴な海獣のように、老人が髪をたらして、海の中から息を吹き返した。
老人は、しばらくその見えない目で、あたりを窺った。そのあと、曇天にかすむ太陽を見上げた。老人は、目を細めた。白くくすんだ光。それは、彼の意識を上へ上へと高めた。
「そこにいるのか、太陽め。頭の上で、いつも私をあざ笑うお前」
老人の口に、荒れる海水が入った。老人は、よだれと共に吐き出した
「お前は、私を助けられぬ。彼らを助けなかったのと同じように。お前は命を育み、奪い、それでいて、無表情、無関心なのだ」
老人の頭は沈んだ。うねる波が、あとからあとから押し寄せる。
カメはどこかへ消えた。本来の姿に戻ったのかもしれない。海の生き物、本能で水の世界を求め、家路をたどり、小さな藻を食べる、しがない生き物に。生き物は、紺の奥底へ沈んだのだ。老人が足をかいている、その下の、さらに下へ。
「お前になど、用はない!」老人は、太陽に向かって指を突き出した。「はじめっからそうだ! 私は、私のやり方であいつらを探しに行くからな。闇に飲まれようが、それが私の見る世界なのだ!」
吠える老人の下では、二匹のカメが、円を描いて踊っていた。
「ねえ、ようやく戻って来られたよ、君。砂と火の玉、それで僕は、喉を詰まらせ、思考もつまったんだ。けれどさ、波が君の声を、僕のところに運んでくれたんだよ」
相手のカメは、ゆったり泳ぎ回る。
「私は、なにもしてないわよ。ただ泳いでいただけなの。水中光芒の柱、冷たい黒闇、そのあいだを、さまよっていた。おそろしくつまらなくてね……」
カメたちは近づいたり離れたりして、まわりまわる。それは、やがてちいさな渦を作り出した。
空気と水のはざまにいた老人は、だんだん海の内部へ引きずり込まれた。
いままで罵詈雑言喚いて、熱された石のように頭を赤くしていた老人は、ふいに微笑みを浮かべた。
「やっぱりそうか。海にいると思ったのだよ。我が妻、娘、息子たち。そして我が同胞たちよ。いつも君らは、私にいたずらを仕掛けるよな。わかっていたさ、そうとも、だって私は、君らをよくよく知っているのだから……」
それ以上、言葉は老人の口から出てこなかった。
彼は、海の闇に抱かれ、ようやく安息を手に入れた。沈んでいく老人のまわりを、カメが取り巻き、泳ぐ。二匹は、つかず離れず、まわったまま、愛と試しの視線を交わした。
老人は、海の底で沈黙した。かつて愛していたものたちが溶け消えた海の底に。朽ちた骸をカニが這い、藻がすべてを覆いつくす。
紺の世界で、彼らはようやく帰途についた。