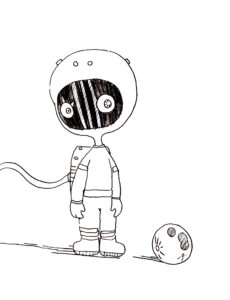あなたの目の中に、木漏れ日が見える。奥の方で蝶が飛んでいる。あなたは、私を抱え上げ、戦の影を背後に隠す。
おかえり。
小さな犬が言う。おかえり。
「私を迎えに来てくれたの?」
「いいや、ちがうよ」あなたは言った。「ちょっと寄っただけなんだ」
透明な波が、小さなカニを攫って行く。
私も、そこへいくのかしら。白い子犬が私の踝をぺろぺろ舐める。
「戦争は、おわったの?」私は訊ねる。
けれどあなたは、遠くの森を見て、涙を流す。あなたは、ただ、笑うだけ。
「綺麗にまっすぐ生えた二本の足を持つ者は……」
遠くで歌が聞こえる。
「塞げぬ傷口を抱えて生きることを、覚悟しなければならない……」
■
チョコレートが食べたいと、1番が言った。
それはよくない、そう言ったのは、55番だった。
「どうして」と1番。
「歯が砕けるからだよ」と55番。
白い犬が、首輪を光らせる。「おしっこ!おしっこ!」
「見てよ。白玉が、おしっこだって!」
一番年下の3番が笑い転げる。
「どうしても、チョコレートが食べたいの!」1番は叫ぶ。
55番は、ため息をついた。
「遠くの町に、チョコレートの城がある」
1番は目を輝かせた。
「けれど、僕の町とチョコレートの城は、仲が悪いんだよ」
「戦争だ! 戦いだ!」白玉が言う。「戦いだね! おしっこ!」
「早くそこでやっちゃいなよ」1番は、白玉のお尻を軽く叩いた。アンモニアの匂いが漂った。
「戦いじゃないよ」55番は言った。「戦争じゃないよ。ずっと続いている、変えられないことなんだ」
「それって、なあに」3番は、鼻をほじった。
「例えば…」55番は、顔を上げた。「あそこに見える、オレンジ色の月を、僕たちはとても大事にしているだろう?」
「チョコレートの城では、真っ赤な血を大事にしているって、聞いたことがある!」1番が思い出したように叫んだ。
「違うよ。緑の蛙だよ」と3番が口を出す。
そこで、「しっ!」と55番が口に指を当てた。
後ろの壁から、誰かが歩いてくる音が聞こえた。硬く、こつこつ、と。
「チョコレートの靴の音だよ」3番が、じゅるじゅるよだれを垂らしながら言った。
「匂いはする?」と1番。
「静かに、静かに」と55番。
チョコレートの靴の音は、去っていった。三人は、ほっと息を漏らした。けれど、白玉が「おしっこできた!」と叫んだので、また体を強張らせた。
チョコレートの足音が近づいて来る。
三人と一匹は、ばくばくする心臓をおさえるように、膝を一生懸命抱えて、じっとした。
すると、ぶごぼご喋る声が聞こえた。同時に、濃厚なカカオの香りが漂ってきた。
(チョコレートの兵士だよ)
小声で1番が言った。55番は、黙っているよう、無言で首を振った。
それから55番は、近くにあった、溶けて固まったジェリービーンズの塊を遠くへ投げた。ちょうど、ずらりと並ぶ缶の一つに当たって、缶は遠くへ遠くへ転がった。チョコレートの兵士たちは、はっとそちらへ足を向けた。
足音は遠ざかっていった。
「ぱあ!カカオ、カカオだったね!」口を55番に塞がれていた白玉は、息を吐いて言った。
「でも、食べ物がなくなっちゃった」
3番が、哀しそうにジェリービーンズが飛んで行った方へ顔を向けた。
「平気だよ」55番は言った。「まだ、僕たちには行っていないところがあるから」
「チョコレートの城に行くの?」こわごわ、けれど、ちょっと好奇心を混ぜて、1番は言った。
だが、55番は、厳しく首を振った。
「あんなところに行かなくても、僕たちは生きていけるんだよ」
「本当に?」1番は疑問の色を浮かばせる。
「そうだよ。さあ、立ち上がって。もうそろそろ行かなくちゃ。お月さまが沈んでいくよ。あの方向に行くんだ。僕たちのことは、あのオレンジ色の月が見守ってくれているから」
「本当にそうなの?」1番は、汚れた服をはたいた。「もしかしたら……」
「ううん。大丈夫。だって、ずっと見てくれているもの」55番は、強く頷いた。
3番は、よろよろ立ち上がった。「お腹が空いた」
そんな3番を、55番は背負うことにした。白玉は、1番に抱えられた。
「大丈夫。2番みたいな目にはあわないよ」
みんなは、55番の言葉に、無言で頷いた。
オレンジ色の月が、埃っぽい道路を照らす。
「血を信じる? カエルを信じる?」
1番は、崩れた道路の縁を歩きながらそう歌った。
「お腹が空いた」55番の肩の上で、3番が呟く。
「お話を聞かせてあげるよ」
55番は、石を蹴りながら言った。白玉は、「待って!相棒!」と追いかけた。
「あるところに、緑色の世界があった。空気は甘くて、さらさらと流れる、透明な道があった。それは、水と呼ばれていた」
「おいしいの?」3番は訊ねた。
「そうらしい。水は、ずっと流れる道となって、しまいには、月が帰るところまで続いていたんだ。そして、月の美しさに気づくと、ずっとそこで、地面を洗って過ごすことにした。ざざあ、ざざあ。水はそうやって、月について歌ったんだ」
「歩きたい」
「いいよ」
3番は、55番の背中から降りた。白玉が、きゃんきゃん吠えて、3番を追い掛け回した。3番は、その真っ白な綿毛を、ぎゅうと抱いて、ちょっと齧った。「わあ! わあ! 食べられた!」
「そこにいくの?」道の端を歩く1番が訊ねた。
55番は、少し考え込んだ。まるで、大切なものを宝箱の中から見せようか、考えるように。けれど、その宝箱の蓋は、ゆっくり閉じられた。
「まっすぐ進む」55番は言った。「食べ物がなきゃ、なんにもはじまらないから」
1番は、「チョコレートの城」と言いそうになったが、黙っていた。
3番が、白玉との追いかけっこをやめて、55番のところへ戻って来た。
「緑の世界は、それでどうなったの?」
「一人のおじいさんが、やっつけちゃったんだって」
「ええ~」3番は、どうでもよさそうに言った。
「おじいさんは、戦いをしたんだ。本当の戦いだよ。武器を持って、やっつけたんだ。偽物の緑を」
「本物はどこにいったの?」と1番。
「わからない」首を振って、55番は答えた。
「お月様が、知ってる?」3番が訊ねた。
「そうかもしれない。でも、そうじゃないかもしれない。だって、おじいさんは、こっそり月から隠れて戦ったから」
「隠れられるの?」
1番は、浮かぶ大きなオレンジ色の月を見上げた。白玉は、遠吠えをした。
「最初は、出来たと思ったんだって。でも、やっぱり逃げられなかったんだよ。おじいさんは、偽物の緑を倒したらね、月に呼ばれたんだ。ざざあ、ざざあって歌う、水のところにね」
「そして?」と3番。3番はくたびれて、その場でうずくまった。
だから、他の2人も立ち止まった。蟻が、一匹、地面を歩いた。
「呼ばれたおじいさんは、仲間に出会ったんだ。いなくなったと思っていた仲間にね」
「本当に!?」蟻を見るためにしゃがんでいた1番は、飛び上がった。「本当にそうなの!?」
「聞いた話だと、そうなんだ」
55番は、蟻を目で追いかけた。わかっていた。1番がなにを考えているのかを。
1番だって、わかっていた、55番がなにを望んでいるのかを。
わかっていないのは、3番と白玉だけだった。
「2番……」
1番が呟いた。とたん、わかっていなかった3番が、すべてを察した。
「会えるの? 2番に、水が、ざざあって歌うところで!?」
55番も、本当はそう言いたかった。けれど、慎重に言葉を選んだ。何回も、同じことが起こったから。
「2番は、チョコレートのところに行ったから、わからないよ」
「でも、会えるかもしれないね?」3番は、目を輝かせた。「行かなきゃ。ええと、み……、水、水のところに!」
「見て!」
55番は、遠くに光る、七つのテントを見つけた。「食事をとろう。月が沈む前に、早く!」
彼らは駆け出した。白玉は、きゃんきゃん吠えた。
「待って! 待って! おいて行かないで! かわいい僕を、おいて行かないで!」
豆の焼ける匂いがした。それから、どろりとしたグレープジュースの匂いも。あとは、ぐでっとした何かの肉が、毛皮付きで、テントの外であぶられていた。
「だれかいますか」
55番が言うと、右のテントから、背中の曲がった少女が出てきた。
「はあい。どうしたの。まあ、小さなわんちゃん」
白玉は、飛び上がってあいさつした。「遊ぶ? 遊ぶ? 遊ぶ?」
「四獣翻訳輪だわ。壊れているのかな。同じ言葉しか言わないね」彼女は、光る首輪を見て言った。
「ちょっと間抜けだからだよ」55番は教えた。
「ふうん」と少女。「変な名前ね。でも、気に入った。私は、薔薇の公園からここまで来たの。薔薇って、みんなは私を呼ぶわ」
1番は、なにか聞きたそうな顔をしたが、55番が先に言った。
「お腹が空いているんだ。なにか分けてもらえると助かるんだけど」
「いいわ。とてもつらいもの、飢えるって」
薔薇は、中央で煮立っているグレープジュースを、錆びた缶に入れた。
「さあ、ひとまずこれを。ぐるぐる空いたお腹の穴に、それはそれはしみるわよ」
三人は、少しずつ飲んだ。けれど、一口飲むと二口。二口飲むと、四口飲みたくなった。
「しみるといったでしょう?」下から、薔薇は笑った。
「おかわり!」3番が叫んだ。とたん、盛大なげっぷをした。
「まだまだあるけれど。もうおしまい。やめたほうがいいわ。満腹って、とてもつらいもの」薔薇は言った。
55番は、あたりを見渡した。
「他の人は?」
薔薇は、人差し指を唇に当てた。
「まだなの。まだ起きてはだめ」
「どうして?」と1番。
「まだ形になっていないからよ。月が―あの忌々しい月が、力を奪うの。立ち上がれるのは、さんさんと輝く太陽さまが登ってきたときだけ」
「君は?」すぐさま55番が訊ねた。「君は平気なの?」
薔薇は、地面に伏せるようにしながら、肩をすくめた。
「私は、薔薇の公園から来たのよ」ずいぶん上から目線な言い方だった。「だれにも負けはしないの」
「そうかいそうかい」55番は、さっさと離れた。
遊ぶ3番と白玉をその場に残し、1番が後をついてきた。
「どうして不機嫌になるの?」と1番。
55番は、さっと振り返った。そして、小声で言った。
「彼女はわからないけれど。テントにいる人たちは、きっと、太陽さまを胸に抱えている者たちだよ」
「……太陽さまって、なんでも焦がしてしまう子ね」
「そうだよ。チョコレートの城は、太陽さまを嫌っているけれど。どうもおかしい」
「どうして?」
「グレープジュースを飲んだだろう。あれは、チョコレートの城でしか作られていないものなんだ。どうして太陽さまを胸に抱いている人たちが、グレープジュースを作っていたんだろう?」
「もしかして、罠?」1番の髪が、ぴりりと逆立った。
「どうしてそう思うの」
55番は、ちらちら薔薇を見ながら言った。薔薇は、白玉と三番を、抱えるように撫でていた。
「わかんないけど。あたしたちが飢えていることを知っていて、あたしたちをチョコレートの城へ送ろうとしたんじゃない? 満腹にしてさ」
「なんのために」
「チョコレートの城を、あたしたちにスパイさせる気かも。恩を売ってさ」
1番の考えは、妥当なように思えた。55番の首の毛は、ぞわりと立った。
「僕らは、水が歌うところに行かなくちゃいけないんだ。チョコレートの城になんかいかないよ」
55番は、はっと口をつぐんだ。1番が、じっと見つめる。
「やっぱり。最初から行くつもりだったんだね。……み、み、水の話をする前から」
観念して、55番はため息をついた。なにか言う前に、1番が口を開いた。とても辛そうに。
「……55番は、2番を、死んだと思ってる?」
はっきり言うことを躊躇った。55番は、そのことを口に出して確かなものにしたくなかった。
「どうだろうね」それだけ言った。
「ねえ、チョコレートの城にも、行く価値はあったんじゃないかな」
小さく鋭く、1番は言った。「2番は、もしかしたらそこにいるかもしれないよ」
「だめだよ、1番」55番は首を振った。「戦わなくちゃ。自分の欲望と」
「欲望なんかっ!」
1番は怒って、55番からもテントからも離れていった。
白玉と3番と背の曲がった薔薇は、仲良く追いかけっこをしていた。
55番は、その様子を見ながら、ぶらさがっている毛皮付きの肉へ近づいた。
ほとんど骨だったが、脂の匂いにそそられた。グレープジュースで腹は膨らんでいたが、心の穴は埋められなかった。もし、上等な肉が、香ばしい焦げが、なめらかな脂が、口の中を、喉の奥を通って行ったら、この穴は塞がるだろうか。55番は手を伸ばす。一滴、透明な脂が落ちて、じゅわっと炎を誘った。
「なにをしているの?」
55番は、手を引っ込めた。
薔薇が、下から目を合わせてきた。
「なんの肉かなと……」
「太陽さまに差しあげるものよ。よそ者は触れてはだめ」
「君はいいの?」
責任逃れをするがごとく、55番は言った。
薔薇は、低いところでにこにこ笑った。
「だめに決まってる。私は、すべてを花にするの。そうしてみんなは、頭が重すぎて頭を垂れちゃうのよ。みんなは、だれよりも低くなるの。あたしよりも、さらにさらに」
「危ない!」白玉が叫んだ。
見ると、3番が、火の中から棒を抜き出して遊ぼうとしていた。
「やめろ!」
55番が駆け寄ったのと同時に、3番の髪に炎が燃え移った。3番は、すぐに理解できず、55番の怒声に飛び上がった。熱が頭を支配した途端、3番は悲鳴を上げた。
55番がはたき消そうとしたとき、薔薇が飛び出し、3番の頭を抱え込んだ。薔薇の腕の中で、3番はくぐもった泣き声を上げた。二人は、がっくりと膝を落とし、みるみる小さくなった。
「3番? 3番!」
55番は駆け寄った。白玉が興奮して、吠えて飛び跳ねる。55番は、地平線から眩しい光球が現われるのを見てとった。
朝だ。太陽さまの世界、朝がやって来る。
「3番をよこせ!」
腕の中に隠れた3番を、55番は薔薇からもぎ取ろうとした。
けれど、3番の姿は、どこにもなかった。
あったのは、薔薇と同じように背の丸まった、手の平ほどの小人だった。
「ほら、言ったでしょ。小さく、小さくなるのよ」
3番の頭には、ひらひらと白い花びらが揺れていた。薔薇の頬に、黒い涙の跡がこびりついている。長年のものだ。日の光が強まり、彼女の顔があらわになっていく。よぎれてくたびれて、涙だらけの、そして、光り輝く二つの瞳が、彼女の顔を飾っていた。
55番は、震える手で3番を包み込んだ。3番は、眠っているように静かだった。
その時、テントの中で衣擦れの音がした。55番の身は強張った。
起きる。太陽さまを胸に抱く者たちが。
何も言わず、55番は駆け出した。白玉があとをついて来る。小さなかぎ爪の、かちゃかちゃいう音だけが、朝焼けの世界にこだまする。
55番は振り返らなかった。1番のことも呼ばなかった。なぜなら、太陽さまを胸に抱く者たちに見つかってはならなかったからだ。
「お月様のところへ。お月様のところへ。そうすれば、治るはずだ」
独り言のように、55番は呟いた。
すると、背後に迫る、不規則な足音が聞こえた。白玉が吠える。
55番は死に物狂いで走ったが、乾いた地面が、足の裏を切った。
やがて前に躍り出たのは、背の曲がった少女だった。
「去れ! 去ってくれ!」55番は、3番を包む手を胸に引き寄せた。
薔薇は、だが、首を横に振った。
「薔薇の公園に行けば、なおしてもらえる。頼んでみるわ」
「そんなこと、どうして信じられる」
薔薇は、まっすぐ55番を見つめた。
「私も治してもらいに行くからよ。それが噂なのか本当のことなのか、確かめに」
ちりちりと、55番の腕が痛みはじめた。太陽さまだ。太陽さまが、胸に抱かぬ者たちを焼き殺そうとしているのだ。
「お月様のところへ行かないと。僕たちは死んでしまう」
「山のお腹を通るのは?」薔薇は、先にそびえる鈍色の山に顔を向けた。「太陽さまは、あそこまで手が伸ばせないわよ」
55番は、お礼を言わなかった。そのまま走り出した。白玉がへえへえいってついて来る。薔薇も一緒に。
みな、無言だった。荒い息遣いだけが、互いの存在を教えた。やがて山の懐に転がり込むと、焼けただれた肌を冷えた日影で癒した。
55番は、痛みにあえいだ。汗ばむ手の中で、3番がくたびれていないか心配した。そして、置いてきてしまった1番のことも。
「もう一人の子は平気よ」
うずくまる55番の傍で、薔薇は頷いた。
「きっと大丈夫」
薔薇が、腕につけていた金の装飾をとりはずし、搾りはじめた。
すると、手の中から黄金の蜜がこぼれ落ちた。「はやくはやく」
白玉が地面を舐め、次は彼女の手を舐めた。薔薇は、はじめて少し笑い声をあげた。
55番は、黙ってその蜜を受けた。低い位置からだったので、寝そべって舐めた。小さな3番の頬にも、その蜜を垂らしたが、小人は起きなかった。
55番の胸には、3番を燃やしたあの炎がめらめらと動いていた。それは、はっきりと薔薇に対しても向けられていた。だが、蜜を受けたことで、その方向はあっちこっちへ行った。
「薔薇の公園なんて、ほんとうにあるの?」
55番は、低く訊ねた。
薔薇は、白玉とともに地面にうずくまりながら、遠くを見る目をした。
「あるわ。私はそこからきたもの。四角いくぼみ、光る虫、屋根のように広がる葉、それらの中に、透明な道が走っているの。水と呼ばれる、透明な道が」
「水! 水!」
白玉が吠え、薔薇の周りをうろついた。「水だね!? 薔薇!」
「水は、全部お月様のもとへ行ったんだ」55番は言った。「だから、それは嘘だよ」
「そうかも。でも、そうじゃないかも。私が生まれたとき、水があったの。いまはどうなっているか、それを確かめに行くのよ」
55番は、唸って立ち上がった。
「その場所は、どこにあるのかわかるの?」
「私がきた道を戻ればいいの。この山を越えて、まっすぐね」
「君は、太陽さまを胸に抱く者たちと共にいた。どうしてそれが、罠じゃないと言い切れる?」
55番は、1番の言葉を思い出していた。そして、手の中にうずくまる3番のことも考えた。
「私は、運ばれる途中だったのだもの」薔薇は、眠そうにぼつぼつ言った。「私は蜜を生む。蜜は、太陽さまを抱く者たちにとって、とても大事なものなの。太陽さまの涙だと思っているわ。私はそれで、連れてこられたのよ」
55番は、信じようか迷った。だから、最後の質問をした。
「どこへ連れていかれるところだったの?」
薔薇は、一度閉じかけた目を開いた。
「チョコレートの城よ。太陽さまを抱く者たちは、あそこが欲しいの。力を見せつけられるし、なにより、商売になるものね」
「チョコレートの城は、そんなに簡単に滅びないよ」兵士の靴音を思い出し、55番はぶるりと震えた。
「いいえ。倒せるわよ。太陽さまを抱く者たちは、それはそれはチョコレートの城を気に入っていないから。それに、とても強いもの」
「でも……」
反論しかけたとたん、55番は、ある可能性に気づいて、体が硬直した。
自分たちは、そんな彼らに追いかけられているかもしれないのだ。太陽さまの涙を生み出す薔薇とともに逃げているから。
55番は、薔薇をかさぶたのようにしか思えなくなった。傷を再生するために必要な、ががさがさとする煩わしい部分。早く剝がそうとすれば、血が湧き出てくる。3番が目を覚まさなくなる。
山の暗闇に抱かれて、彼らは沈黙の休息をした。
55番は久々にまどろんだが、瞼の裏に浮かぶのは、太陽さまを抱く者たちに焼かれてしまう、1番の姿だった。
■
膝が真っ赤になって、まるでトマトのようだった。トマトを最後に食べたのは、2番がトマト缶を見つけたときだ。あれが全員そろった最後の食事だった。
1番は、汗ばむ膝を掻いた。ひりひりする。首筋にじっとり汗が浮かぶ。光球—太陽さまが、自分を焦がそうとしているのだ。
(大丈夫。真上に来る前に、もっと大きな影を見つければ)
1番は、あたりを見渡した。傍の岩陰は、もうそろそろ狭まってきていた。少し先に山がある。そして、背後には、通ってきた町があった。
1番は、町の方に惹かれた。その奥にチョコレートの城があることは知っているが、それよりも、2番との思い出が、1番を掻き乱した。
2番は優しかった。高い背は、肩車をしてもらうと、ありとあらゆるところまで見えた。
2番は、物を見つけるのがうまかった。トマト缶だってそうだし、スープ缶も、豆缶も、ビスケットや瓶ジュース、グミ、ガム、ジェリービーンズ、ポテトチップスも、どこからか見つけて持ってきた。そして、極上のチョコレートも。
でも、あるとき、訝しんだ55番が言った。
「それ、どこから取ってきたんだ?」
2番は、ちょっとためらった後、諦めて全部地面にぶちまけ、言った。
「チョコレートの城だよ」
その後の55番の怒りようったら、まるで興奮して泡を吹く白玉みたいだった。
「見つかったらどうするんだよ!?」55番は2番の胸をつついた。「みんな連れていかれるぞ! 死んでしまうかもしれないんだ!」
2番は、冷静に手を振り払って言った。
「そんなことはない。彼らは、いいやつらだ」
「なんだとっ」
「少し困った顔をすると、分けてくれるんだよ。ゴミ溜めから」
55番は、たまらず2番の胸ぐらをつかんだ。2番の方が背が高かったが、無理をしてでも55番は詰め寄った。
「仲間がみんな連れ去られたのに、よくそんなことができるな!?」
2番は、瞳を揺るがせたが、1番や3番を見て、静かに言った。
「いまを生きる者がいるんだ。俺たちもだ。腹が減ったら、なにもできない。だろう? 怒ることも、悲しむこともできない。ましてや、闘うことも」
「仲間を攫った者たちの食べ物なんか。食べたくないよ!」
55番は2番を突き飛ばした。それから、どこかへ消えた。
2番は、ちょっと缶を転がすと、物欲しそうにしている3番へ、缶を開けて差し出した。
「毒はない。大丈夫、いつもと同じだ」
「ねえ、2番」1番は、寄って訊ねた。
「なに?」
「これを食べたら、チョコレートの城の仲間になるの? チョコレートの城って、いいところ? それとも、これを食べたら、戦いにいくの?」
2番は、少し考える顔をした。3番が缶の口で手を切りそうになったので、2番は自分の手に中身を出し、3番の口に持っていった。3番は、べちゃべちゃ食べた。
「闘いには行かないよ。この四人で行っても、負けちゃうから」
「チョコレートの城は、どんなところなの?」
「甘い甘い、いい匂いがするよ。それに、みたこともないたくさんの色が、ありとあらゆるところに散らばっている。そのとんがった城は、僕らが大事にしているお月様のことだって、突き刺すように隠しているんだ。とても怖いけれど、とても強烈で、力強くて……あれが自分の心の中にあったらな、と思うよ。とにかく、俺にとっては」
1番は、心の中で城を描いた。そして、だれにも見つからない場所にしまっておいた。
「もし、食べ物が足りなくなったら、あたしも……」
「うん?」と2番。
1番は、急いで首を振った。「なんでもない」
2番は、空になった缶を地面に並べた。それは、必ず五つにしてあった。残りは、2番が「狩り」に行くときにどこかへ捨てて来ていた。缶は、いつも食べ終えたばかりの、新品のものが並べられた。
「3番のお母さんに」
2番は、いつもの儀式をはじめた。小さな缶の前に石を置く。穴の開いた屋根からこぼれる月光の輪が、それを照らせるように、2番は缶の場所を丁寧に変える。
「55番の友人たちに」
2番は、中くらいの缶三つの前に、石を置いた。
最後に2番は、二つの缶の前に、石を置いた。
「僕らの両親に」
2番はそう言って、しばらく、月の光の輪の中にある石を眺めた。
「あたしたちがお月様のところへ行くときは、だれがやってくれるの?」1番は訊ねた。
2番は、ふうむと顎を膝でささえた。
「確かに。そいつは必要だ」
そうして2番は、次の日から三日間、姿を消した。
怒っていた55番も、そのときにはそわそわしていて、2番の帰りを待ち続けた。
「いなくなったりしてはだめだ」55番はぶつぶつ呟いた。
ようやく帰って来たとき、2番の腕には、白い子犬がおさまっていた。
「新しい仲間だよ」2番は微笑んだ。「俺たちをお月さまのところへ連れていってくれる、白玉さ」
1番は、並ぶ缶に触れた。
戻ってきてしまった。発った場所、またここに。
町へ向かう足を、1番は止められなかった。倒れた缶の傍に、ジェリービーンズの塊がある。それは、靴底の跡がついて潰れていた。
チョコレートの兵士がここに来たのだ。1番は、自分がとんでもなく危険な場所にいることがわかっていた。わかってはいたが……。
2番。2番が見たのは、どんな景色?
1番は、そろそろと隠れ家から顔を出した。
遠く地平線の彼方に、チョコレートの城が見える。じりじりと太陽さまが力を発する昼の世界で、チョコレートの城は、依然、堂々とそそり立っていた。それは、まわりを取り巻く、痛むほどの冷気によって、さらに幻想的に見えた。白く、緩やかに渦巻く冷気は、チョコレートの城を優しく包み込んでいた。
2番、2番。行ったきり帰ってこない2番。
捕まってしまったのか、それとも、あたしの知らない間に、贅沢なお菓子を食べているの?
いいや、それはない。2番は、ちゃんと分けるということを知っている。分け与える、その意義を。
であれば、55番の言った通り、やはりもう……手遅れなのだろうか。
今になって後悔する。ああ、55番を置いて来るんじゃなかった。一緒に、水が月の歌を歌う場所へ行けばよかった。
その時、規則的な低い音が聞こえた。
どん、どん。
足音? それにしては大きく、空気がびりびり震えた。
すると、チョコレートの城のてっぺんで、真っ赤な火花が散った。遅れて、どおおんと大気を揺るがす大音声が響いた。
1番は、耳を塞いだ手を、しばらく下ろせずにいた。
チョコレートの城があんな声で叫ぶところを、見たことがなかった。
「2番、なにが起こってるの?」1番は呟いた。
そこで、今度ははっきりと見えた。チョコレートの城から、特大のガムボールが発射されるところを。
向かう先は、太陽さまの方角だ。
太陽さまを、攻撃しているの!?
ガムボールが着弾したところに、火の手が上がった。そして、怒声とともに、なにかがチョコレートの城へ向かって走り出した。
大勢の、太陽さまを胸に抱く者たちだ。なぜなら、特有の金の飾りで身を包み、反射した光が1番の目を射抜いたからだ。
1番は、眩んだ目を瞬いて、なにがおこっているのか見極めようとした。
2番、2番。戦いが起っているの? チョコレートの城は、それほど悪い場所なの?
太陽を胸に抱く者たちと、私たちの町、どちらもどれも、チョコレートの城を嫌って、お互いを嫌っている。どうしてなの? なぜこうなったの? 2番。
あたしたちは、なにをしたのかな? 影に身をひそめながら、1番は考える。あたしたては、なにをしたの? あたしたちの両親、その両親、その両親たちは、なにをした?
1番は、倒れていた缶を元に戻した。地面に潰れて張り付いたジェリービーンズを足でこそげ落とした。
そこで1番は、はっとした。
並んだ缶、その前にあるはずの石が、ひとつなくなっていた。それは、1番と2番の、両親のための石だった。
嘘だ。ここを発つ前は、絶対にあったはずなのに。だれが取ったのだろう。
白玉のことを考えたが、あのまぬけな犬が石を奪う理由が考えられなかった。
1番は、ぽっかり空いたその空間を見つめた。ちらちらと舞い踊る埃を眺め、その一粒一粒に手掛かりがないか、息をひそめて凝視した。
その時、また足音が聞こえた。太陽さまを胸に抱く者の集団が、さっきよりも近づいているように思えた。
ここを去らなくちゃ、1番。自分に警告する。去って、去って。命が惜しければ、ここを去って。
でも、もう一人の頑固な1番が言った。だめ、2番の手掛かりを見つけるまで。ここを去ってはだめ。
いるはずがないのに。
絶対にいたはず。
ここにはこない。
もう死んだ。
石を取ったのは、2番よ。
あたしたちの石を取ったのは。
でも、そうする理由は、
どこにもないはずでしょう?
どおおおんと砲撃音が響く。ぱらぱらと砂が落ちてくる。
そこで1番は、壁の高い場所に、ひっかき傷を認めた。
寂れた椅子を引きずって来て、どうにか近づくと、傷は数字を示していることがわかった。ほのかにチョコレートの香りがする。
そう、数字には、チョコレートの欠片がところどころに詰まっていたのだ。
数字は、1番にこう訴えた。
2―1=0
1―2=―1?
1番は、心臓が痛くなった。どん、どん。太陽さまを胸に抱く者の足音よりも、断然早く脈打っている。
傷をなぞる。そこにこびりついたチョコレートを、わずかに舐める。
刺すほど甘く、かぐわしいカカオの香り。
1番は、その数字を繰り返し繰り返し読んで頭に叩き込み、椅子を降りた。
そして、砲撃音がやんでいるのをいいことに、隠れ家を飛び出した。
■
酔うようなリンゴの香りが、55番の頭をくらくらさせた。
山の坑道を、薔薇が案内したが、それはリンゴの汁が絶えず流れ込む、死んだ坑道だった。
55番は咳き込んだ。甘酸っぱい香りが、胸を満たして吐き気がした。
後ろでは、白玉がリンゴ汁を舐めて驚いていたが、ずっと続くこのべちゃべちゃした道に飽き始めていた。
「チョコレートが食べたい!」白玉は言った。
「死んじゃうよ」
口呼吸しながら、55番は言った。やっぱり、あの四獣翻訳輪は壊れているんだろうか。あの翻訳輪は、自分がごみ箱から見つけ出してつけたものだが、粗悪品だったに違いない。かわいそうな白玉。喋らなければ、かわいいだけだったのに。中身のない言葉が放たれただけで、間抜けになる。自分たちと同じだ。
「あとどれくらいあるの」
前をかしいで歩く薔薇に、55番は訊ねた。
「もっと、もっと。一日くらいかかるわ。でもあきらめちゃダメ。リンゴはもうすぐ終わるから」
薔薇の声は、前へ向かって響いた。
「このリンゴは、どこから?」と55番。
「山の中に工場があるって聞いたわ。世界中のリンゴを集めて、絞っているって。赤、黄色、銀、ピンク、青紫、いろんなリンゴよ」
進むたび、55番は胸が苦しくなった。それは、雑多に混ぜられたリンゴ汁のせいでもあるが、1番のこともだった。
「リンゴがおわったら、少し休まないか? 1番が追いかけてくるかもしれない」
薔薇は、くるりと振り返った。
「たしかに私たちは、まっすぐ歩いてきた。でも、分かれ道があったのを見たでしょう。1番がもしこの山に入ったとして、もしこの坑道に入ったとして、もしまっすぐに進んだのなら、待ってもいいと思うけれど。……私、山へ入った時、もうあの子のこと、あきらめたんだと思ったわ」
「たしかにそうだ」
55番は、苦々しく頷いた。あの時は、けれど、焦っていたのだ。手の中の3番のこと、3番を変えてしまった薔薇のこと、それから、追いかけてくるかもしれない太陽さまを胸に抱く者たちのこと、それらが、前へ逃げろとせっついたのだ。
「でも、あんな別れ方をしたくなかった。1番は仲間なんだ」
「喧嘩ね。よくある話ね」薔薇は、曲がった胸のあたりを静かに掻いた。「でも、リンゴがなくなるまで歩くのに、一日かかるわ。そうすると、距離があくと思うけれど」
55番は、言いたくなかったが、仕方なく答えた。
「わかった。じゃあ、そろそろ足を止めよう」
少し進むと階段があったので、彼らはそこで腰を下ろした。55番は、包んでいた手を広げ、3番の様子を見た。
頭の花びらが、体温で少し萎れていた。55番は、険しい顔で3番を撫でた。どんどん仲間が消えていく。あいつも、あいつも、2番、1番、そして3番までいなくなってしまうのか……。
「あなたは、どこへ行くつもりなの?」
薔薇が、足元にうずくまりながら訊ねた。
55番は、躊躇ったが、やがて言った。
「僕らは、お月様を胸に抱く者だ。お月様は、水を呼んで、歌を歌わせている。その場所に、僕らは行くんだ。そこでは…………」
「そこでは?」薔薇は、鼻を鳴らす白玉を抱え上げて問う。
「そこでは、いなくなった者に会えるという話があるんだ。僕らは、それを確かめるために行くんだ」
「ふうん」
薔薇は、無味乾燥な返事をした。
「君にはわからない。お月様がどれほど美しいか。どれほど力を持っているか」
「あなたにはわからないわ。薔薇の公園が、どれほど愛しい場所か。どれほど恐れられている場所か」
薔薇は、下から真剣な瞳をのぞかせた。腕に白い子犬を抱くその姿は、古い絵画のようだった。
彼らは、一人一つの段を使って、丸まって寝た。濃厚なリンゴの香りが鼻や胸の中に居座り、55番は眠れたものではなかった。
けれども、それはいつものことなのだ。しっかりきっかり眠れたのは、はて、2番がまだいたころだった。やつが背中を合わせ、交代で見張りをしていた時のことだ。55番は、背後を2番にまかせっきりにした。それが、互いのためであったからだ。不必要な配慮をしない。
……だが
2番は、どこかへ消えた。オレンジ色の月が昇った時、2番の姿はなく、55番は地面で大の字になっていた。
「2番はどこだ?」
眠っている1番と3番、それに白玉に声をかけた。「2番はどこだ!」
わかったのは、オレンジ色の月が沈んでも、2番は帰ってこないということ。次の日も、次の日も。さらに次の日。白玉を連れて帰って来たあの日よりも、さらに幾日も過ぎた。
2番は、とうとう戻ってこなかった。
連れ去られたんだ。
日が立つにつれ、その声は55番の中で大きくなり、やがて確実なものになった。
チョコレートの城のものを、あれほど持ち出すからだ。見つかってしまったのだ。
それか、月が出る前に、取りに行って捕まったのだろうか。僕らを驚かせるために?
だが、そこで合点がいかなくなった。2番は、なぜ見張りをやめてまで、チョコレートの城へ行ったのか?
55番は、それを考えるたび、みぞおちががんがん重く煮えたぎるのを感じた。だから、その考えは隅っこに寄せ、蓋をした。
1番には言わなかった。いや、だれにも言えないだろう。2番は僕らを捨てたのかもしれない、なんて。
「チョコレートが食べたい」
1番は、たびたびそう言った。2番がいないことが、当たり前になったころになっても、1番は言った。それが2番との懸け橋であるかのように。
55番は答える。
「だめだよ。歯が砕けるよ」
だめだよ、だめだよ。砕けてしまう。身を滅ぼしてしまう。あいつも、あいつも、2番も消えてしまったのだから。
けれど1番の瞳には、どこか羨望のようなものが、チョコレートの城を見る時に浮かぶのだった。
だめだよ、だめだよ、1番。あんなところに行っては、身を亡ぼすよ。
いつも夢の中で、2番が出てくる。2番は、ごみ溜めから拾ってきたたくさんのお菓子を腕に抱え、一歩一歩、後ろへ下がる。
「ごめんな、55番。ごめんな」
それから、2番の口は、チョコレートの手でふさがれて、消えてしまうのだった。
汗をかいて飛び起きた。生え際がじとじとする。思わず手で拭う。
そのとき、3番が手の中にいないことに気づいた。55番は叫んだ。
「ここよ」
見ると、階段下で、薔薇がなにかをしていた。手を包んでいる。
「なにしてるんだ! 返せ!」
「しーっ」
薔薇は、きつく首を振った。
55番は、滑るように階段をおりた。危うく白玉を踏みそうになり、白玉は飛び起きた。
「なんで!? どうして! 起きる?」
「なにしてるんだ」
55番は、再度薔薇に訊ねた。
薔薇は、地面に蓋をするように、手の小山を作っていた。その中に3番がいることは、容易に予想できた。
薔薇が、ゆっくり手を除けると、うずくまって食事をする3番の姿があった。
55番は、息を呑んだ。生きている。その狂喜は、喉を押しつぶした。
「お腹が空いて、目が覚めたのよ」薔薇は小声で言った。
だが、3番が食べているのは、リンゴ汁を吸った土だった。
「……君が食べさせたのか?」55番の中で、また薔薇に対する疑心と怒りが生まれた。
「私がこうさせられたから、こうしているだけよ」薔薇は3番を見ながら言った。「こうするのがいいの」
3番はむしゃむしゃ土を食べている。小さな手、小さな口で。
55番は、喉を鳴らした。嫌悪と嫉妬がこみあげる。僕も山のように食べたい。口の中を膨らませるほど、汚すほど。
「3番、3番」
55番は、屈みこんで呼びかけた。
すると3番は、わずかに振り返り、大きな55番に気がつくと、驚いて薔薇の手の影へ後退した。
「大きな声で呼ぶからよ」薔薇はくすくす笑った。「小さいと、なにもかもが大きく感じるのよ」
「3番、聞える? 3番」小声で、55番は必死に訊ねた。
3番は、困った顔をして、さらに薔薇の手に身をくっつけた。
「もうこれくらいにしてあげてよ。きっと、混乱しているんだから」
「君のときも、そうだった?」55番は訊ねた。
「私は、少し大きかったから、何となくわかったけれど。とてもショックだったわよ。三日間は口をきけなかったわ。なにもかも大きくてね。それって、とんでもなく怖いことなの」
薔薇はそう言って、またゆっくり両手を閉じた。怯えた3番緒顔は、薔薇の手の中に消えた。
「君はどうしてそうなったの? だれにされたの? どうやって、いまのように大きくなったの?」
55番は、矢継ぎ早に質問した。薔薇は、煩わしそうに頭を振った。
「あんまり話したくない」と薔薇。「面白くないことだもの」
「でも、3番にとっては大事なことだ!」
とたん、薔薇の目に影が差し、いまにも消えてしまいそうなほど、体を縮めた。
55番は、気づいて謝った。「……悪かったよ。言いたくないことだったんだよね」
薔薇は、ふるふる涙をこぼした。
「いいの。ただ……薔薇の公園に行くの」呪文のように、薔薇は言った。「薔薇の公園に。薔薇の公園に」
■
2―1=0
1―2=―1?
数式が、1番の頭をごちゃごちゃにした。そして、溝に詰まっていたチョコレートの欠片も、同じく頭をごちゃごちゃにした。
チョコレートの欠片を信じるならば、あれは、チョコレートの兵士が書いたと考えられる。チョコレートにまみれた爪付きの籠手で、あの壁に傷をつけたのだ。
でもそうすると、あの数式の意味がわからなくなる。書かれた場所からするに、2番くらいの身長の兵士が、あれを書いた。それって、どういう意味?
もしあそこにチョコレートの欠片がなければ、2番からのメッセージである可能性が高かったのに。
2―1=0
1―2=―1?
1番は、頭が痛くなってきた。
なりたたない数式は、暗号と思えた。だとしたら、使われている数字は、あたしたちを示している? 1番と2番を?
そうしたら、こう読めなくはないか。
2番は1番を失って、0になった。
1番は、2番を失って、マイナス1番になった。
最後は「?」がついているから、問いなのかもしれない。
つまり、
1番は、2番を失って、マイナス1番になった?
悲しんでいる? とたずねたいの? 1番は、じわじわと熱い雫を目に溜めた。
もしこれが、2番からの問いでも、チョコレートの兵士からの問いでも、どちらも同じことだ。
どちらも、1番の気持ちを理解していない。
あたしは、怒っている。わざわざ悲しんでいるか問う、その姿勢に。
だが、涙を浮かべる理由は、もう一つある。信じたくもないある考えが、浮かんだからだ。
それは、
2番はチョコレートの兵士で、
チョコレートの兵士が2番ではないか、
というものだった。
オレンジ色の月が昇る。わずかに欠けた、オレンジの月が、
1番は、ゆらりゆらりと、町を出た。砲撃はすっかりやんでいる。戦場は遠くになったみたい。
もしくは、太陽さまを胸に抱く者たちが、負けたのかも。だって、彼らは、お月様のもとでは生きられないから。
もしチョコレートの城に行けば、2番に会えるのか考える。あそこにメッセージを残したのは2番かと、聞けるのか考える。
でも、一人で行く勇気がなかった。2番だったら行けただろうに。2番と一緒だったら行けただろうに。
55番を追いかけるしか道はない。いま、お月さまが見守っているうちに。
一人は心細い。みんなで通った道も、一人だととても広く感じる。
毛穴という毛穴から、焦りの汗が噴き出してくる。なにも食べていない。だれもいない。はやくおいつかなければ、踏みつぶされた蟻のようにぽっくり簡単に死んでしまうだろう。孤独と、飢えと、哀しみの重圧によって。
「55番と考えよう」1番は一人呟いた。「55番なら、違うことを思いつくかも。あの数字のことを」
「そうすれば、あたしもすっきりはっきりしてくるわよね?」
「でも、2番はどこにいるの?」
「水が歌うところにいるわよ」
「でも、それって……」
「違うわ。ちゃんとして。前のことに集中して」
1番は、顔を上げた。月が煌々と夜道を照らす。その下に、くっきりと山の稜線が見える。まるで、蓋を切り取られた缶の口みたいに。ここが缶の中で、お月様がいる空が、缶の外。あたしたちは、缶の中を、ずっと、ぐるぐるぐるぐる回るのだ。
「55番に、必ず会えるよ」1番は、1番に言う。「缶の中にいるから。外には、出られないから」
1番は、歩き続けた。サンダルの裏がぺらぺらにはがれて、何度も躓いた。やっと、七つのテントが並んでいたところに来たが、燃えカスだけがあって、グレープジュースの鍋も、太陽を胸に抱く者たちも、だれもいなかった。
幸いであり、不幸であった。1番の腕は、1番の体を抱きしめた。誰かと話をしたかった。こんな広い缶の中で、すっかりひとりぼっちなのだ。萎れて潰れて最後に残った、コーンの一粒みたいに。
1番は、燃えカスに近寄って、なにか食べ物がないか探した。
黒くなった枝が、ぼろぼろと手の中で崩れていく。思わず舐めてみたが、苦いのなんの。すぐに吐きだし、そこで力尽きて、寝そべった。
お月様がじっと見ている。柔らかい月光が毛布になって、1番をくるむ。
1番は、目を閉じた。
誰かが後をつけているとも知らずに。
■
どれほど時間がたったのか、リンゴの坑道にいる55番たちは、さっぱりわからなかった。
いまは、太陽さまの時間か。それともお月様の時間か。
そして、もう一つ分からないのは、1番の安否だった。
階段でリンゴ汁を吸った泥を丸めながら、55番はついに立ち上がった。
「来ない、来ない。やっぱり、迎えに行こう」
階段下にいた薔薇は、顔を上げた。白玉の背中に3番を載せて、彼女は遊んでいた。
「戻るの? 行ったり来たり、大変ね」薔薇は、他人事のように言い、白玉の頭を撫でた。「リンゴは甘い! 3番、かわいい!」白玉は言った。
「君にはどうでもいいことだろう。でも僕は、もう仲間をなくしたくないんだ」
「それはわかるわ。私も、仲間から話されてしまったもの」薔薇は、白玉を見ながら言った。「でもね、ずっと後ろに戻って追いかけていたら、先に進めないと思うわよ」
「なんだって……」55番は一段一段降りるたび、歯ぎしりを強くした。
薔薇は、振り返った。
「1番に、あなたは何て言ったの? 行先を教えた?」
55番は、立ち止まった。
「水がお月さまの歌を歌う場所に。そこに行くって。みんなで行くって、言ったんだ」
「ざざあん、ざざあん」
3番が、小さな声でつたなく言った。
久しぶりのその声に、55番は、薔薇の横に、がっくり膝をついた。
55番の頭を、薔薇は撫でた。
「平気。1番は、ちゃんとそこに来るわ。まっすぐすすもう。振り返らないで。約束の場所で会うんだから」
55番は、なにも言わなかった。どろどろ涙を流した。それが、55番の最後の涙だった。
「……行こう」
立ち上がって、55番は、暗い先を見た。「会いに行こう。1番に。2番に。48番、106番に。会いに行こう。会いに行くんだ」
55番は、ぶつぶつ呟きながら、歩きだした。嗚咽は、リンゴの匂いに押されて出てこなかった。
薔薇がついて行く。白玉は駆け足をしたものだから、背中の3番はしっかり首の毛をつかんでいなければならなかった。
「どこ行く? どこ行く?」白玉は吠える。3番は、きゃあきゃあはしゃぐ。
薔薇は鼻歌を歌って、右へ左へと傾いで歩く。
「会いに行くんだ」55番は、白玉に向かってそれだけ言った。
「会いに行こう! 会いに行こう! 会いたいねえ! 会いたいねえ! みんなに会いたいねえ!」
ついに、リンゴの香りは消えた。かわりに、まるくつやつやとした岩が現われはじめた。
「こんなところを、太陽さまを胸に抱く者たちは、通ったの?」55番は、薔薇を見下ろして言った。
「半分に別れてとおったのよ」と薔薇。「半分は山の上を。半分は、山の下を」
「どうしてそんなことを」
「前にもいったじゃないの」薔薇は、踊るように歩きながら言った。「チョコレートの城へ戦いをしに行くんだって」
55番は、気づかれないように首を振った。
「どうしてだろう? なんでだろう? チョコレートの城は、それほど商売になるんだろうか」
「なるのよ。戦いは、お金になるのよ」
薔薇は、肩でまあるい岩に触れながら言った。
「3番がおしっこした!」
白玉が悲鳴を上げて駆けて来た。背中の三番はけらけら笑い、白玉の首筋からは、黄色い汁が滴っていた。
薔薇は、鼻をつまんで、きゃっきゃっ笑った。「飲み過ぎたのよ。食べすぎたのよ」
白玉がうるさく吠えるので、55番は、3番をつまみあげた。
「3番、おしっこしたくなったら、地面でするんだ」小さな声で、気を付けて、55番は話した。
3番は、頭の花びらをゆらめかせ、あっちへこっちへ斜めに頷いた。「漏れそうだったんだもん」
「漏らしたんだよ! 漏らしたんだよ!」白玉は飛びあがって抗議をする。
「土をかければ、臭くなくなるよ」
薔薇は、せっせと白玉の首に土をかけた。「あひゃ! あひゃ!」と白玉。
55番は、3番をそうっと自分の肩に立たせた。
「僕のところでは、お漏らししないで。いいね?」
3番は、こくりと頷いた。
55番は、訊ねなかった。花小人になってからの3番の記憶のことを、なにもかも。きっと、こんがらがっていると思うから。もしかしたら忘れていると思うから。
忘れるって、時に便利だ。時に痛いのだ。
55番は、3番をのせた肩を動かさないようにしながら、歩き続けた。
道は、右へ左へ、上へ下へ伸びていた。分かれ道もいくつかあった。そのたびに、薔薇が空気を嗅いで、「こっちよ、こっち」と誘導した。3番も、同じようなことをした。
「風が来てるよ。光があるよ」3番は嬉しそうに言った。
「なにが見えるの?」
55番は、目を凝らしたり、匂いを嗅いでみたりしたが、闇と湿った土の匂いしか感じられなかった。
「見えやしないわよ」薔薇はけらけら笑った。「あなたはところで、風が見えるの? 光は見えるの?」
「見えるわけないじゃないか」
「じゃあ、同じね」
薔薇は笑い、3番は、「急げ急げ!」と、55番の襟足を掴んで叫んだ。
千歩は歩いただろうか。突然、頬に詰めたい風が吹いた。これには、55番も歓声を上げた。「出口だ! 外だ!」
青白いひし形の出口が、そこにはあった。55番の頭より少し上の、一人分が這って出て行けるほどの穴だ。
白玉が一番に駆け上がり、外へ出た。次に3番が、55番の肩から岩へよじ登って、出て行った。
55番は、薔薇を振り返った。それから、地面に四つん這いになった。
「僕を土台にして。よじ登れるか?」
薔薇は、散ってしまいそうな儚い笑みを浮かべた。それは一瞬であり、さらに、薄明りにわずかに浮かぶ、非現実的なものであった。
薔薇は小さな足を55番の背中に乗せ、岩を掴んだ。何度も何度も失敗した。55番は、そのたびに背中を押し上げた。とうとう、薔薇が出口の岩を掴んで、足を話した時、55番は、薔薇の足の裏に手を添え、ぐっと押した。一つかみの草のように軽かった。
薔薇は、ひし形の向こうへ消えた。
55番は、遠くなった背後を見つめた。なにもない、真っ暗闇を。それから、ぐいぐいと力強く登っていった。
外は群青に染まっていた。オレンジ色の月は空におらず、太陽もいなかった。
「きっと、山の後ろにいるのよ」薔薇が振り返って言った。「月はね」
「じゃあ、もうじき太陽さまが登って来るんだ。それまでに、距離をかせごう」
55番は、3番をつまみ上げながら言った。
「見て!」
白玉が、遠くに落ちている何か黒いものに近づいた。「チョコレートだよ!」
「おい、食べちゃダメだよ!」
55番は慌てて駆け寄った。
白玉は、食べもしなかったし、鼻を近づけて匂いを嗅ごうともしなかった。白玉がやったのは、ただ、きゃんきゃん吠えることだけだった。「兵士だ! 兵士だ! 兵士の死骸だ!」
「チョコレートの塊みたいに見えるけど」
薔薇は、四つん這いになって、黒い塊をのぞき込んだ。「甘いのね。チョコレートって、こんなに甘い匂いなのね」
55番は、ごくりとつばを飲み込んだ。すると、3番が、腕を伝っておりてきた。
「食べちゃダメ?」3番は問うた。
55番は、わずかに欠片を取ったところだった。匂いを嗅ぎ、舐めてみた。
刺すような甘さと、独特なカカオの苦さが、口と鼻腔にぶわっと広がった。
55番がなにか言う前に、もう3番はチョコレートの塊にかぶりついていた。まるで虫のようだった。55番も、ぼっきり塊を折って、ほおばった。おいしかった。とても、とても。
「ああ、兵士が~」と白玉。
薔薇は、貪り食う二人を、じっと見つめた。
それを見た55番は、これだけ言った。
「怪物にはならないよ」
それを聞くと、薔薇も手を伸ばした。
気持ち悪くなるくらい食べても、塊は、まだ55番の背丈の半分以上あった。
55番は、白む東の空を眺めながら、最後の服を脱いだ。
「これに全部包んでしまおう。これなら、飢えることはないぞ!」
空が仄かに黄色く染まるまで、三人は地面にこびりついたチョコレートをすっかり55番の服に包んだ。袖をぐるっと結ぶと、立派な食料袋になった。どんなものよりも価値がある、大切な包みになった。
「日陰を探さなくちゃ。溶けないようにね」
「あなたもでしょ」
薔薇は下から優しく言った。
55番は、仲間のそれぞれの顔を見た。月を胸に抱く者は、自分一人だけだった。
「そうだね」55番は小さく言った。
彼らは、前方の森へ、進路を向けた。
「薔薇の公園があるの」薔薇は跳ねて言った。「水もきっとある。楽しみね」
■
1番が目覚めたときに思ったのは、口の中の違和感だった。味がする。しょっぱかったり、甘かったり。
群青の世界に焦点があって来ると、燃えカスのあたりに、色が山ほどあった。
それは、食べ物だった。豆缶、コーン缶、スープ缶、半分になったドーナツ、固まったジェリービーンズ、数枚のビーフジャーキー、ポテトチップスのかすが入った袋、他にも、飴、グミ、グレープジュース、キウイジュース、トマトジュースがあった。
1番は、飛び起きてまわりを見渡した。だれもいない。テントも張られておらず、寝る前と同じ、1番だけだった。違うのは、突如現れた食べ物の山だった。
1番は、一つ一つ丁寧にたしかめた。どれも本物で、舌に触れると味がした。おかしいのは、自分の腹が満腹であると告げていることだった。
「だれかが、あたしに食べさせたんだわ」
「具合は悪くないわ」
「誰かがあたしを生かしてくれているの?」
「55番? 近くにいる?」
1番は、また周囲を見渡した。岩と、遠くの山、そして西に沈みかけているオレンジの月があった。55番は、いなかった。
「水が歌うところに行けば、会えるわよ。そういうことでしょ、55番」
泣きそうになりながら、1番は、食べ物をかき集めた。ふと、肩掛け鞄が落ちていたことに気づき、1番は、すべてをそこにしまった。
「都合がいいわ。よすぎるくらい」
不安に思いながら、1番は立ち上がった。そこで、肩掛け鞄の紐のところに、チョコレートがくっついていることを知った。
1番は、爪でこそげ落とそうとしたが、なかなかとれなかった。
「兵士が使ったんだ」
1番は、1番に言い聞かせた。「使っただけよ。どこかで死んだよ。絶対に」
1番は、山へ歩き出した。
太陽が山の上に姿を現すには、時間がかかった。1番はその間に、早歩きで山へ逃げ込んだ。
山の木々は、きな臭い葉の匂いに満ちていた。1番は、ジェリービーンズの塊を取り出し、その激しい人工香料を思いっきり嗅いだ。
「さあ、登っていくよ」1番は、1番に励ましの声をかけた。
山の勾配は急ではなかったが、ときに根っこや岩や、滑る土が、行く手を阻んだ。1番は苛立ちながら、泥まみれになって進んだ。
やがて、七色をした建物が見えてきた。仄かにリンゴの香りがする。けれど、稼働している気配はなく、山と同様、しんと静まり返っていた。
どこかで、じゃあじゃあという音がした。近づいていくと、太いパイプが、じゃあじゃあと赤褐色のリンゴ汁を垂れ流しているのを見つけた。それは、血管のようになって、山の中を枝分かれしながら流れていた。
1番は、手のひら一杯分、リンゴ汁をすくってのんだが、とまらなくなって、流れに直接顔をぶちこんで飲んだ。それからは、流れを伝って歩いた。
木が、太陽を隠した。1番は歩き続けた。歩きながら、自分に話しかけた。そうすると、二人いるような、三人いるような、いいや、十人、百人いるような気がした。そうすると、なにも怖くなかった。話をやめることの方が、恐ろしかった。
「55番はすぐそこで待っているわよ」
「水のところへ行ったんだ。そこで会えるよ」
「あんた、道、わかっているの?」
「この流れが、もしかしたら、水なんじゃない?」
「55番が言うには、水は透明だって。これは血よ。リンゴの血よ」
「太陽さまを胸に抱く者たちは、血が好きだったわよね」
「違うわ。チョコレートの城の者たちよ」
「虹の工場は、チョコレートの兵士が作ったのかな?」
「おいしかった?」
「おいしくはなかったね」
「喉が渇いた」
「じゃあ、飲もう」
1番は、リンゴ汁を飲んだ。また歩いた。喋った。飲んだ。少し食べて、また歩きだした。
お月様が出ると、おかしなことに、1番は眠りはじめた。それは、いままでめったにやったことのないことだった。
山を下り終えたのは、光球がまた沈んだときの話だった。
1番は、平地になったところで足を止め、林立する木の麓に座り込んだ。
「会えなかった」
1番は、しくしく泣いた。
「会えるよ」
誰かが言ったので、はっと顔を上げた。
でも、それが自分の声だと気づくと、とたんに頭を抱えた。
「あーあ、リンゴの流れも、なくなっちゃったよ」
「工場からでた、あまりもの。ひどい味だったから、よかったんだよ。さあ、お月さまのところへ向かおう。そっちに行くって、55番、言ったじゃない」
「もう無理。一人だもん。一人でばっか喋って。おかしくなっているよ。食べ物なんか、もらわなきゃよかったんだよ。そうすれば、すっかり諦めがついたのにさ!」
そこで、ぎくっとした。思っていたよりも大声を出していたようで、1番の声は、木に跳ね返り、遠くまで響いた。
1番は立ち上がった。人の影を見た気がしたのだ。
進んでいくと、あっちにも、こっちにも、大勢の人影が、木の間に見えはじめた。行進しているかのようだ。こちらへ向かって。
1番は、止まった。じっと待っていても、向こうはやって来なかった。青黒い影は、オレンジの月明かりに輪郭を縁取らせた。
五歩手前まで、1番は一つの影に近づいた。石のようだった。
「わ!」
1番は叫んだ。なにも起こらない。こんどは腐った枝を投げつけた。こつん、と硬い音がした。反撃はしてこなかった。
「あなたはだれなの」
1番は、さらに近づいた。すると、見覚えのある靴が目に入った。
チョコレートの兵士の靴を、その影は履いていた。爪付きの籠手だって、兵士のものだ。
まわりに立っていたのは、すべてチョコレートの兵士だったのだ。歩いた姿勢で立ち止まっている。
1番は、一歩一歩退いた。そして駆け出した。
「待て」
だれかに腕を掴まれ、1番は悲鳴を上げた。体がもちあがり、足が宙を蹴った。喉がかれるくらい、叫んだ。
「静かに! 静かに!」
くぐもった声がした。そして、濃厚なチョコレートの香りも。目の前には、チョコレートの兵士の顔があった。くり抜かれた一つの目、その奥に、どくどくと赤く光る瞳があった。下へ生える五つの牙、その向こうで、隠れた呼吸音がした。
「静かに。ここへ来たことが、みんなに伝わってしまう」
1番は、声が出なかった。チョコレートの兵士と会話をしてはいけないと、みんなに教わったからだ。55番、パパ、ママ。それと……。いいや、2番からは教わらなかったかも。
兵士は、1番を地面に降ろした。背が高かった。
「月へ向かって、まっすぐに。きっと会えるよ」兵士は言った。
「あ、お…お…」1番は声を絞り出した。「お、おかしい。おかしい! どうして、なんで!?」
兵士は、なにも言わなかった。ただそこに、じっと立っていた。なにもしなかった。
「おかしい! あたしを助けているの? 罠だ! なんのためにそんなことをするの!?」
「静かに、静かに」兵士は、また諭した。「仲間に会いに行くんだろう。さあ、早く行くんだ。離れ離れにならないうちに。見つからないうちに」
「もう見つかっているじゃんっ」
兵士は、首を振った。
「なかったことにするよ。ここの兵士たちには、近づかないことだ。身も心もチョコレートになっているからね。チョコレートは仲間だよ。みんなに伝えるよ。さ、早く、行った行った」
兵士は、手を振って追い払った。
けれど1番は、身動きが取れなかった。
「……2番?」
兵士は、振っていた手を止めた。
「そいつに会いたいの?」兵士は兜の下で言った。
1番は、兵士の様子を伺いながら、こっくり頷いた。
「だったら、なおさら急がなくちゃ。タイミングって、大事だよ。逃しちゃいけないよ」
「水がお月さまへ歌う場所のこと、2番は信じる?」
「僕が信じているのは、真っ赤な血だけだよ」
1番は、「わかった」と言って、駆け出した。
それから、二度と振り返らなかった。
■
3番は、森の中に入ると、岩から岩へ、枝から枝へ、楽しそうに飛び移った。その様子を、55番は羨ましく思って眺めた。
「待て待て! 3番! かわいい3番!」白玉が、上を向きながら吠えたてる。
「薔薇の公園は、綺麗なところよ」薔薇はずっと公園について話をしている。「光の虫がずっとダンスをしているの」
55番は、頭を振った。もし、薔薇に抱かれて自分も小人になったら、この楽しみを味わえるのかもしれないという考えを振り切るために。
きらきらと、木の葉が隙間から太陽の光をこぼした。3番と薔薇と白玉は、その中を走り回って光の水玉を受けたが、55番は、決して光に触れないようにした。焼けて痛みを負うなんてごめんなんだ。3番、かつての君なら、わかってくれるだろう?
チョコレートを食べ、休憩し、きな臭い葉の雫を飲んで、休憩した。3番と薔薇は、進むたびに、活発になった。光を浴び、水を吸って、風を受けると、さらにさらに肌が輝いた。55番は、さらにだんまりになった。
「もう日が暮れるわね」薔薇は言った。「ほら、見て。木が紫になってる」
「それがどうした」
55番の言葉に、薔薇は顔を上げた。
「チョコレートの食べすぎよ」
「だからなんだ! 僕は光を食べない、土を食べない、風も食べない! 君たちと違うんだ! ほっといてくれないか」
「わお、わお! 55番が怒っているよ!」白玉がきゃんきゃん吠えた。
「お腹が空いたんだ」55番はしゃがみ込んだ。
薔薇が傍に寄って来て、背中に触れた。追っ払いたかったが、同時に、その体温を感じていたかった。
「あなたを仲間だと思っていないなんて、思っていないわよ」
「けれど、僕は違うんだ。3番も、もう違くなってしまったし」
そのとき、薔薇が息を呑む音が聞こえた。
顔を上げると、丸い葉っぱが宙を浮いていた。
「蓮の葉よ」
薔薇は吸い上げられるように立ち上がった
3番が、いつのまにか蓮の葉の上でふんわりふんわり飛び跳ねていた。頭の花びらが、3番を浮かせているのだ。
「白玉、こっちこっち!」
白玉は、呼びかけに応じ、3番を追いかけた。
「この葉っぱに続いて行きましょう。公園がすぐそこだわ」
薔薇はうきうきして、55番の手を取った。55番は、導かれるがまま、転びそうになりながら、ものすごい速さで駆けていく薔薇について行った。
ついたのは、森の中央だった。光る虫が漂い、蓮の葉が何重にもなって夜空に浮かんでいた。
薔薇は、ほっと肩の力を抜いた。
「薔薇の公園よ」
彼女は、真ん中の方形になっているくぼみを指して言った。
くぼみは、55番が十人並んで寝そべっていても足りないくらいの大きさだった。深さは、ざっと踝くらいだ。
「ここに、水があったの。でも、もう逃げてしまったって」
薔薇は、くぼみの縁石に膝まづいて言った。
「どうしてそんなことがわかるの?」
「ここに書いてあるのよ」
薔薇は縁石を指さした。ぼけた雲のような、変な模様があった。
「やっぱり、お月さまのほうへ行ったんだよ、水は」
55番は、あたりを見渡した。方形からは、細長い道が、5本伸びていた。「この道をたどっていったんだ。この一本なんか、ちょうどお月様の方に……」
「そうなのかもね」
薔薇は、目を伏せた。そして、しばらく、光る虫を眺めていた。
「もっと、綺麗な場所だと思ってた。そうであったはずなのに」と薔薇。
「……じゅうぶんに、綺麗だと思うけれど」
「ううん。そうじゃないの。水もそうだし、公園のこともそう。みんな、私の思い描いた通りにあるのだと思っていた。でも、違っていた。歓迎する花の子たちは一人もいないし、水も、もうないんだもの」
薔薇は、そこで、ぎとぎと涙を流した。その量は、背中が軋む音が聞こえてきそうなほどだった。
「もう少し探してみたら? 花の子、一人くらいいるかもしれないよ」
55番は言ったが、薔薇は、呆けて立ち上がれなかった。だから、55番は、一人で公園内を歩き回った。
お月様の光が、蓮の葉の影を地面に落としていた。55番は、影から影へと飛んだ。
飛ぶたびに、55番は、身が軽くなるのを感じた。そうか、一人って、軽いのだ。
ひととおり飛び終えると、バラの迷路が現われた。
55番は、頭の高さまであるバラの壁を眺めた。そして、いざなわれるように、迷路の中へ入った。
バラは様々な色をしていた。薄黄色、桃、赤、紫、白、そして青。
55番は、バラをそっと撫でた。刺すような痛みが走り、バラは、切られた生首のように地面に落ちた。
だが、そこに本当に顔があることに気づくと、55番は後ずさりした。
顔は、わずかに口を動かした。
「なにをしにきたの?」
55は、ぶるぶる震え、一目散に薔薇の方へ駆け戻った。
「戻れなかった者たちよ」
話を聞くなり、薔薇は言った。
「太陽を胸に抱く者たちにつれていかれて、太陽さまの味方になると、ずっと花のままだわ。でも釈明して、しっかり薔薇の公園の者であると—心はだれにも売っていないと、ここで言えば、花から変えてくれるのよ」
「なにへ?」と55
「それは、それぞれよ」
薔薇は、55を見上げえた。
「しっかり薔薇の公園の者であると認められれば、どんな姿にでも変えてもらえるの。薔薇の公園は、そうやって広がるんだわ」
昔話のように薔薇は語り、ぼんやりと方形のくぼみを見つめた。
「僕らが君の釈明を聞くって言うのは?」
55番は言い、薔薇は「え?」と見上げた。
「僕と白玉、合計四つの耳が、君の釈明を聞く。誰もいなくても、それで証人になれるだろう。3番の釈明も、君がやるんだ」
「……公園以外の者が釈明を聞くなんて、聞いたことがないけど。でも、誰もいないものね」彼女は、また公園を見渡した、
「やってみよう」
55番は言い、走り回っていた白玉を捕まえ、方形の前で胡坐を掻いた。そして3番を呼び寄せた。
3番は、ひょっこり、蓮の葉から顔を覗かせると、伸びた55番の手の上へ、飛び降りた。
薔薇は、落ち着か投げに服の皴を伸ばし、割坐になって、方形のくぼみを見つめた。
「私は薔薇」
薔薇は言いはじめた。
「この血で生まれた、八重の子ども。八重は私を抱えたときに、私を薔薇にした。……そしてこちらは、私が抱えた子、3番」
薔薇は、小さな花の子を手で示した。
「燃える頭を守るため、私はこの子を包んだ。私は太陽を胸に抱く者に攫われ、この花の子も、太陽に追われた。
けれど、薔薇の公園の主、私たちの心は、いつでもあなたのそばにいます。私の友達である55番と白玉が、その証人です」
薔薇は、こちらを振り返った。
「ええ、その通りです!」55番は叫んだ。
「おしっこ!」白玉は言うなり、55番の手にあたたかいものをまきちらした。55番は静かに舌打ちした。
すると、一陣の風が吹き、方形の中央に、つむじ風ができた。その風は見上げるほど大きくなり、お月様をすっかり隠してしまった。月光は霞み、蓮の葉は、ぐらりぐらりとゆれた。
つむじ風は、不思議な匂いを運んできた。55番は、それにむせかえった。
たくさんの生き物、土、風、それと、夜の匂いが、濃厚に混ざり合っていた。その匂いは、55の胸を力強く打った。
それから、誰かがささやくような声を聞いた。
公園の主は、どうどうと髪や肌を引っ掻いた。冷たい涙が、顔を打った。
「主は泣いているの?」55番は、大声で訊ねた。
「これは雨よ!」薔薇は答えた。「主たちは、私たちを確かめているわ!」
3番は、55番の肩の上で顔を洗い、全身を洗った。55番は、初めての雨に、肌が泡立った。白玉は、大口を開けて、雨を飲んだ。
風と雨音に混じって、誰かの笑い声がした。それは、薔薇のものだった。薔薇は、そのか細い腕で、自分自身を抱いていた。いいや、もしくは、なにか大いなる存在に抱きしめられているようにも見えた。それに、55番は、びりびりと内側が震えた。
55番は、自分も真似して、自分を抱いてみた。雨が口に入り、喉を鳴らした。
「私は雨、おまえはだれ?」
囁き声が、さらに大きくなって耳に届いた。55番は、答えるべきものとして、こう言った。
「僕は、55番」
「私は雨、水となって、川となって、海となるもの。おまえは、なにへなる者?」
「僕は、川を知らぬ者。海を知らぬ者。けれど、月への歌を、あなたが歌う場所に、行こうとする者です」
「しからば、あなたの手と足、私と同じものにしよう」
何を言う間もないまま、55番の手は、ぐんにゃり溶けていき、足もすっかり液化した。55番は、怖さよりも、強烈な力を感じ、息を呑むことしかできなかった。
公園の主は、雨風をまとって去ろうとした。55番は、風へ手を伸ばした。
「待って! 僕らは、会えますか? 1番や、2番、他の者たち、失われた友人たちに!」
「あなたは自由に世界を駆ける。あなたは自由に追うことができる。あなたは自由に見つけることができる」
最後の一粒が鼻の頭に当たった瞬間、55番はどっさり後ろに倒れ、気づけば目をあけていた。
夜空が広がり、蓮の葉が広がり、そして光の虫が揺蕩っていた。
方形には、湿り気のある苔が生えていた。
「ねえ?」
薔薇の声がした。
55番がすっかり起き上がると、背中が曲がったままの薔薇がいた。
「どうだった?」55番は訊ねた。
薔薇は、くっくっくと笑った。そして、体をぶるぶると震わせると、背中にひびが入った。
銀色をした四枚の羽が現れ、やがて青黒い少女が薔薇の皮を脱いで出てきた。背中はすっかり曲がったままだが、少女は満面の笑みを浮かべた。蝶は、大いなる風を吹かせて、飛び上がった。
蝶は、歓声を上げて、蓮の葉よりも上を、飛び回った。
55番は、3番と白玉を探した。すると、真っ白に輝く子犬が足にじゃれついた。翻訳輪がはずれていて、ずっと嬉しそうな吠え声をあげていた。それでも、55番は、白玉がなにを言いたいのかわかった。
「きれいだよ。かわいいよ」55番は、望み通り、言ってあげた。
すると、肩の上を、はさみを持ったたくさんのカニが這ってきた。真っ青なそのカニは、甲羅に月光を反射させた。
カニは、55番の目の前で集まり、子ども大の背丈になるまで高く自らを積むと、ようやくその顔をあらわにした。
カニの集団から出たのは、幼い3番だった。
「見て見て! 青くて、かっこいいでしょ!」
55番は、こっくり頷き、瞳を輝かせたまま、自分も手の先をじっくり見つめた。そうすると、ぐにゃぐにゃと形が代わり、色が失われ、透明な流れが放たれた。
水は、カニを包み、蝶を攫い、高く高く、登っていった。蓮の葉に乗った白玉は、遠吠えをあげ、水の頭の上で波に乗った。
オレンジ色の月が、てらてらと水の中で輝き、水の鼓動をさらに加速させた。
「海へ」
水は言った。蝶も、カニも、くすくす笑った。
「海へ」
「月の歌を歌う!」
水は、長く長く尾を引き、方形から伸びる月への道をたどって、水たちが歌う場所へと向かっていった。
■
息も絶え絶えになって、1番は、森の出口で座り込んだ。
もうじき、お月様が天頂にやってくる。ずたずたに引き裂かれた1番の心は、お月様を眺めても、癒されなかった。前は、眺めていれば、その優しい光に身を包まれ、傷など徐々に塞がれたのに。
あたしも、チョコレートの兵士になればよかった。そうすれば、この苦しみも味わうことなく、甘い人生で終われたんだわ。2番みたいに、心を全部チョコレートに捧げれば、簡単にできたことだった。
それなのに、どうして? どうしてあたしは生かされているの? 2番、どうしてあたしを、生かそうとするの?
励ましの言葉は、もう出てこない。立ち上がって、水が歌うところに行きたい。でも、もう体はくたくただ。永遠にたどり着けないのではないかという恐怖が、重い石となって足にくくりつけられていた。
「なんて自分勝手なんだろう!」
1番は、鞄を叩きつけた。
「2番の馬鹿! 両親の馬鹿! 月も太陽も、チョコレートも、みんな馬鹿よ。残ったコーンのあたしのことなんか、だれも助けやしない。みんなほったらかして、自分で立ち上がれ、ほら頑張れって言うだけなんだわ! でも、あたしだって、最後に残りたくなんてなかったのよ!」
1番は、伏して乾いた涙を流した。
空虚になった瞳に、美しい幻影が映った。
月の前を、何かが通り過ぎたのだ。その凛として透明な輝きは、1番の胸を静かに叩いた。
あれは、なんと言うのだろう。渦を巻くその澄んだ流れは、青と銀のきらめきをまとっている。そして、透き通るような遠吠えを発して飛んで行くのだ。
来て。来て。それは無言で誘う。
それには、名前がない。
ああ、と1番は気づいた。名前がないものは、まだたくさんあるようだ。
1番は、よろよろと起き上がった。あれの名前をつけるのは、あたししかいない。いいや、他の者に譲ってたまるものか。
あれは、あたしのものだ。
1番は、無言で鞄をあけると、すべてのものをがつがつと食べた。ビーフジャーキーを引きちぎり、コーン缶もスープ缶も貪り食って、腹いっぱいになるまで食べた。
ポテトチップスのカスをひとかけらも残さず舐めとると、1番は、軽くなった鞄を引っ提げて、駆け出した。
あの輝かしい者たちが飛んでいく方へ。
■
大きな月が空の真ん中へたどり着いた。月は全てを見下ろしている。風がオレンジ色になった、その世界を。砂塵が舞い、かつて白銀に煌々としていた月を変えてしまった、その世界を。
月は、眺めた。ざあざあと哀しみの歌を歌う海に、新たな流れがやって来るのを。
その新たな水は、蝶のさざめく笑いと、カニの途絶えることのない行進と、轟く吠え声を伴って、悲愴な海へ、怒涛の勢いで流れ込んだ。
海は押し流され、またさらに波を強くした。それでも、澄んだ流れはおさまりを見せなかった。海岸は、大嵐になった。
その風は、砂塵をかき混ぜ、古い木をなぎ倒し、がらがらと、積もり積もった缶や袋や瓦礫を吹き飛ばした。
そのごみは、遠く、固まったチョコレートの兵士たちの顔にぶつかり、張り付き、太陽を胸に抱く者たちのテントに入り込んだ。
戦前にたつ双方の戦士たちは、この突然の嵐に顔を上げた。
それから、その顔に、ぼつぼつと大粒の雫がぶつかった。だれもその名前を知らなかったが、しばらくの間、誰一人、剣を、爆薬を相手に向けようとしなかった。中には、突然の空の涙に、きゃあきゃあ悲鳴を上げて逃げ出す者もいた。
月は、また、そんな荒れ狂う海岸に走ってくる一人の少女も見つけた。
少女は、カニに囲まれ、足を取られ、みるみる海へ持って行かれた。
すると、一羽の蝶がやってきて、彼女の肩に手を添えて、こう言った。
「やっぱりね、ほら、会えたじゃない」
すると、美しい水が、渦を巻いて、少女をすっぽりと包み、抱え上げた。
「1番、1番!」
水は言った。水は、ぐにゃぐにゃと一つの顔を形作った。
それが55番だとわかった少女は、頬に張り付くカニのくすぐったさもあって、笑みを漏らした。水の瞳に、それがはっきり反射した。蝶と、揺れる木々、それから、遠くの戦いも。
足元で、白い犬が鳴いている。おかえり、おかえり、そう言っている。
すると、波が何重にも重なり、遠くの波が、ぐるりと四つの人型を作った。
朝焼けが後ろから近づいて来る。黄金の光が、海を瞬かせる。
「迎えに来てくれた」
水が、少女に向かって言った。
水は、人型の方へ流れていき、三つの人型を抱きしめた。カニが波にさらわれていく。いいや、もしかしたら、波が迎えに来てくれたのかもしれない。
あたしも、そこへ行くのかしら?
少女の足元で、白い犬が鳴く。風が、前から、後ろから押し寄せる。
どこからか、歌が聞こえる。
「綺麗にまっすぐ生えた二本の足を持つ者は……」
ふと、水がさざめく場所で、一人の萎びた老人が岩に座っていた。歌は、彼が歌っていた。
老人は、白い目を少女に向けた。すっかりお月様と同じ色になった目を。
「迎えに来たのか?」老人は言った。
「いいえ、ちがう」少女は言った。「ちょっと寄っただけなの」
「戦争は、おわったのか?」老人は訊ねる。
少女は、遠くの森を見て、涙を流した。少女は、ただ、笑った。
老人は、歌を歌った。
「綺麗にまっすぐ生えた二本の足を持つ者は、塞げぬ傷口を抱えて生きることを、覚悟しなければならない……」
「名前をつけにきたの」少女は言った。
「俺も、同じようなことを思って、ここに来たよ」
老人は、斜め上を向いて、頷いた。
「あの綺麗なものは、あたしのものよ」
「ああ、ああ、名づけるがいい。俺も名前を付けた。傷を塞ぐために」
「それで、塞げたの?」と少女。
老人は、静かに笑った。
「ちゃんとしまっておけばな。ずっとここに座ることもなかったのだよ。もしくは、隠してはいけないことを隠し続けなければ、一人でこそこそ戦うこともなかったのだよ。娘を失うこともなかったのだよ。偽物の緑を追うこともなかったのだよ。月に見つかって番人を命じられることもなかったのだ。でも、君は知っているのだろう。あの名前を。そしてこれから、どうすればやっていけるのかということも」
「いいえ、わかりっこないわ」
少女は目を細め、後ろから登って来る血のような太陽と、海へ薄らいでいく月を眺めた。
「あたしたち、一人でなにかをやったりしないわ。あたしたち、ただ歌いに来たんじゃないわ。甘い救いをもらいにきたんじゃないわ。あたしたち、何度でも星を変えにきたの。だからここに、みんなで来たの」
(2023)